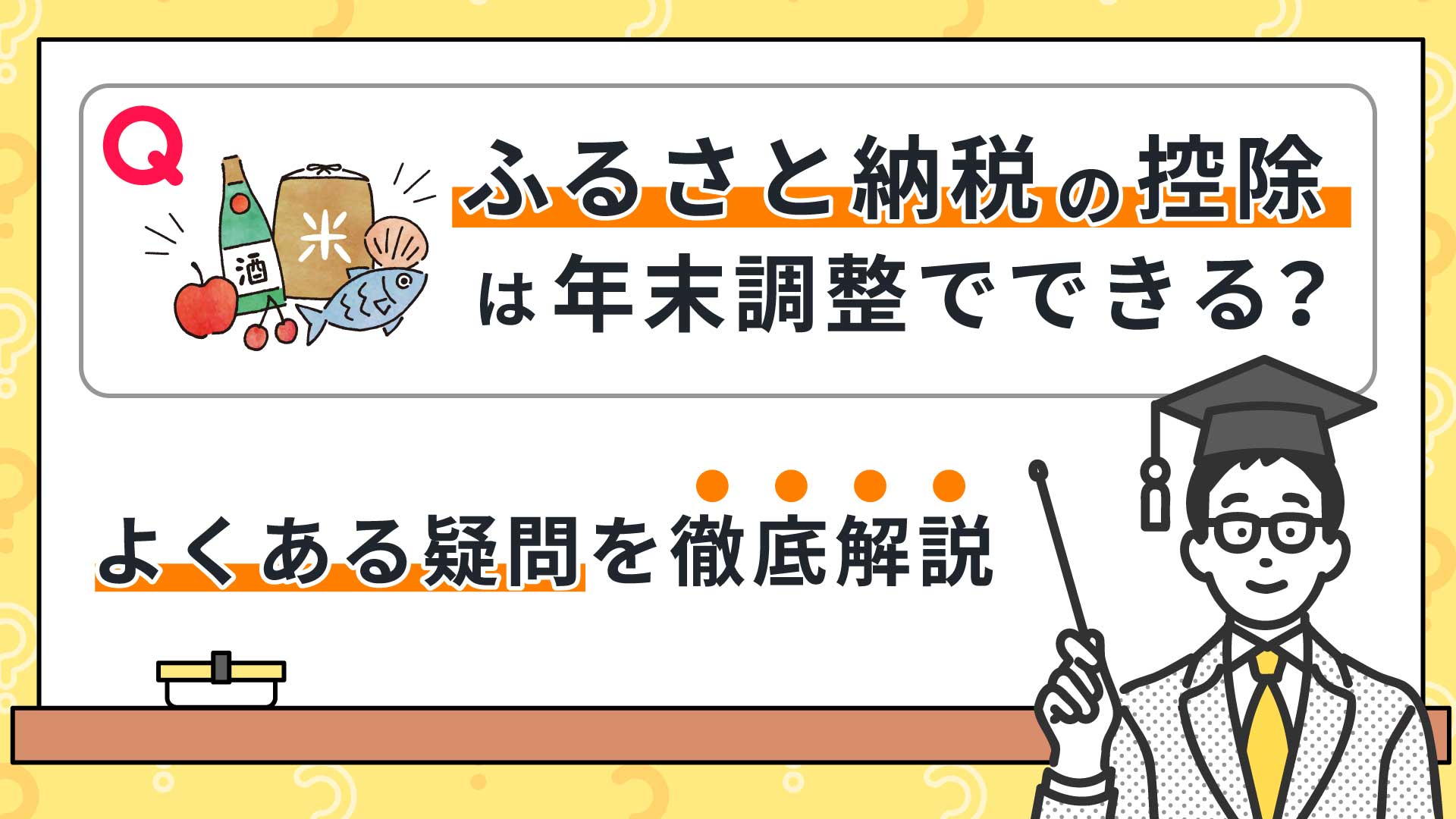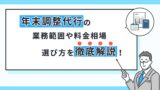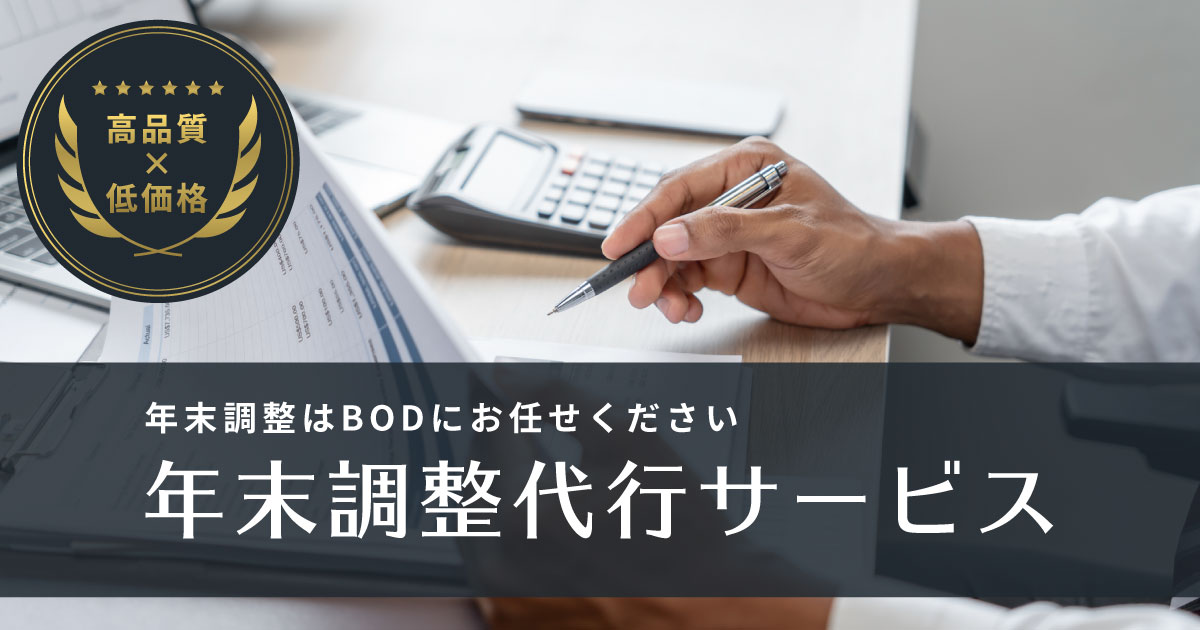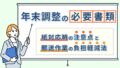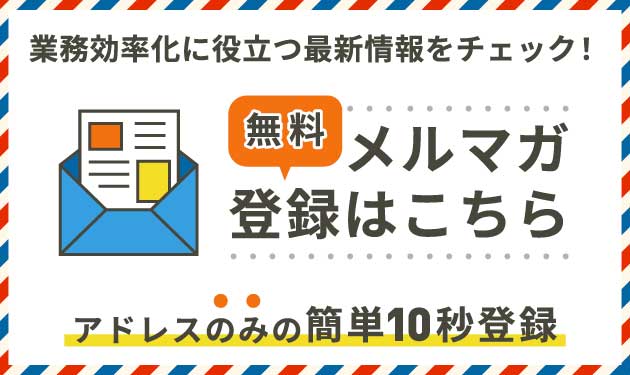2025年10月~ルール変更「ふるさと納税 ポイント付与の廃止」とは
「ふるさと納税って、年末調整で控除されるの?」
年末調整の時期になると、少なからずこんな疑問が従業員から寄せられます。ただでさえ慌ただしいこの時期、人事・労務担当者にとっては、毎年繰り返される問い合わせ対応が大きな負担になりがちです。
加えて2025年10月には、「ポイント付き返礼品の禁止」といった制度改正も予定され、従業員の関心や質問は今後さらに増えることが見込まれます。本記事では、「ふるさと納税の控除は年末調整でできるのか?」という基本的な疑問から、控除の仕組み、よくある誤解、そして制度変更のポイントまでをわかりやすく解説。合わせて、人事・労務担当者の負担を軽減するための具体的な対策や、外部サービスの活用方法についてもご紹介します。
▼毎年、手間のかかる年末調整をアウトソーシングしませんか?詳しくはこちらから!▼
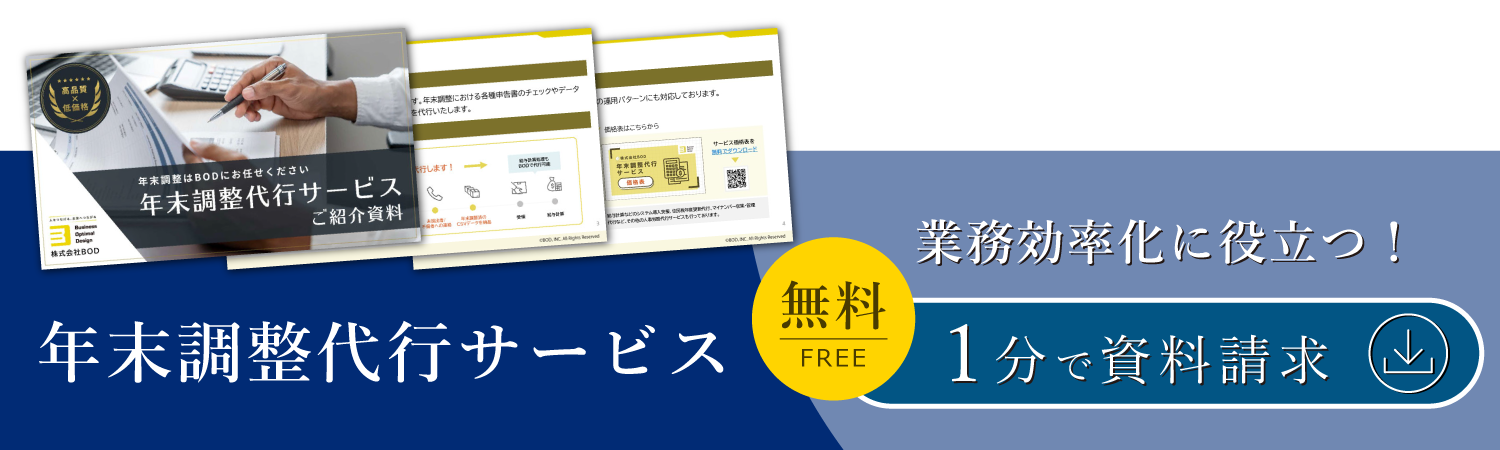
ふるさと納税の仕組みを整理しよう
| ふるさと納税 | 自治体に寄付をすることで税金の控除を受けられる仕組みのこと |
ふるさと納税とは、応援したい自治体に対して寄付を行うことで、所得税・住民税の一部が控除される制度です。実質的な自己負担は2,000円で、それを超える金額は一定の上限内で控除の対象となります。
寄付先は出身地に限らず、全国の自治体から自由に選ぶことができ、地域の特産品などを「返礼品」として受け取れる点も、多くの人に利用されている理由のひとつです。
ただし、年末調整の仕組みの中ではふるさと納税分を直接処理しないため、個人で控除を受けるための手続きが別途必要となります。これを知らずに、会社へ関連書類を提出すれば反映されると誤解するケースも少なくありません。
適切に控除を受けるためには、寄付金受領証明書など書類の提出先を把握し、確定申告あるいはワンストップ特例制度を活用する必要があります。
2025年10月~ルール変更「ポイント付与の廃止」とは?
2025年10月から、ふるさと納税の制度に関して新たなルールが導入されます。総務省の通達により、寄附に伴う「ポイント付与」などを行う仲介サイト経由の募集が禁止されることになりました。
出典:総務省「ふるさと納税制度に係る募集適正基準の見直し」
具体的には、「ふるさと納税をしたら▲▲ポイントを○○%還元」というような形式が制度の対象外となります。これにより、一部のふるさと納税ポータルサイトでは、現在の仕組みが大きく変更されることが予想されます。この改正の前に、「今のうちに寄付しておこう」「廃止される前に利用したい」と考える人が急増する可能性が高く、いわゆる「駆け込み寄付」が加速する見込みです。

例えば──
「制度が変わると聞いたけど、何がどうなるんですか?」
「10月までに寄付しておいた方がいいと聞いたけど、控除の手続きはどうすれば?」など
内容も多岐にわたることが予想され、人事・労務担当者の対応負担が増す可能性も否定できません。あらかじめ改正のポイントを把握し、社内での情報共有や案内体制を整えておくと混乱を防止できるでしょう。
ふるさと納税の控除額はどう確認する?
ふるさと納税を行った際、控除を受けるために必要な確認ポイントは以下の通りです。
●寄付金受領証明書
寄付先の自治体から発行される証明書で、控除申告の際に必要となります。
●確定申告書の試算
確定申告を行う場合、この申告書で寄付金控除額の試算が可能です。
●住民税決定通知書
翌年に交付される通知書で、寄付金控除が正しく反映されているかを確認できます。
控除額や寄付金の反映に疑問や不備がある場合は、早めに自治体や税務署に問い合わせることをおすすめします。
年末調整でふるさと納税の控除ができない理由
給与所得者の所得税調整を一括で行う年末調整では、なぜふるさと納税が反映されないのでしょうか?
年末調整は、会社が把握できる給与や社内制度に基づいて税額を精算する仕組みです。一方、ふるさと納税は個人が自由に行う寄付であり、会社側では寄付先や金額を確認できません。さらに、寄付は12月末まで可能なため、年末調整時点で正確な金額が確定していないこともあるからです。
年末調整の仕組みとは?
会社は毎月の給与支払い時に所得税を概算で源泉徴収し、年末に1年間の給与総額や保険料控除、扶養控除などをもとに正確な税額を算出します。こうして生じた源泉徴収税額との過不足が調整され、還付・追徴される仕組みが年末調整です。ふるさと納税のように個人的に行った寄付金控除は、会社の年末調整枠では扱われないため、別途手続きが必要となります。

なぜ年末調整でふるさと納税は控除されない?
年末調整で扱う情報は、給与所得や生命保険料など企業が一括して管理できるものに限られます。一方、ふるさと納税は個人が自由なタイミングで行える寄付であり、その金額や時期は企業がコントロールできません。さらに、寄付が12月最終日まで可能なことから、年末調整の締切時に最新の寄付額を正確に反映するのが難しいのです。このため、会社を通じて控除されず、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きが必要となります。
▼まずは価格表を参考に、ご検討ください!▼

▼年末調整代行について必要な情報が網羅されています。こちらの記事をご覧ください。▼
ふるさと納税の控除を受けるには
~ ワンストップ特例制度 or 確定申告、どちらが必要でしょうか? ~
ふるさと納税で控除を受けるには、手続きを正しく行う必要があります。選べる方法は2つ。 「ワンストップ特例制度」を利用するか、「確定申告」で申告するかです。それぞれの条件や手順を確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度の利用条件
「ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要な給与所得者で、以下2つの条件を満たす方が利用できます。
●1年間に寄付した自治体が5つ以内であること
※同じ自治体に複数回寄付しても「1自治体」として数えます。
●確定申告が不要であること
※個人事業主や年間2,000万円以上の給与所得がある方、医療費控除などで確定申告が必要な方は対象外です。
この制度を利用すれば、確定申告をせずに住民税からの控除を受けることが可能です。
【注意点】
・寄付のたびに自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しなければなりません。
・申告特例申請書は寄付をした翌年の1月10日までに自治体へ必着が条件です。間に合わない場合は、確定申告による控除申請が必要になります。
・申請後に住所変更があった場合は、必ず「変更届」の提出が必要です。
確定申告が必要なケース
次のいずれかに該当する場合、ふるさと納税による控除を受けるには確定申告が必要です。
●個人事業主や不動産収入があるなど、もともと確定申告が必要な方
※給与が2,000万円を超える/副業収入が年間20万円を超えるなどのケースが該当します。
●1年間の寄付先が6自治体以上になる方
●ワンストップ特例の申請をしていない、または提出期限(翌年1月10日)に間に合わなかった方

確定申告を行うことで、所得税からは還付、住民税は翌年度分から減額という形で寄付金控除が受けられます。必要書類(寄付金受領証明書など)を準備し、e-Taxまたは税務署窓口で申告手続きを行いましょう。
人事・労務担当者が取るべき対応とは?
年末調整の時期が近づくと、ふるさと納税に関する問い合わせが例年より増えることがあり、特に控除の仕組みや手続き方法についての質問が目立つ傾向があります。そのため、人事・労務担当者の業務負担が重くなるケースも想定されます。
こうした状況に備え、事前準備と情報共有が重要です。以下のポイントを押さえて、スムーズな対応を目指しましょう。
よくある質問に備える「社内FAQ」の整備
ふるさと納税に関する代表的な疑問やトラブル例をリストアップし、わかりやすく回答をまとめたFAQを用意することが効果的です。FAQを社内イントラネットや共有フォルダに掲載し、担当者だけでなく他の社員もアクセスできるようにすると、問い合わせの一次対応がスムーズになります。

誤解を減らす社内告知テンプレの工夫
「年末調整ではふるさと納税の控除ができない」「控除を受けるにはワンストップ特例か確定申告が必要」などのポイントを、わかりやすく伝える社内向け告知文例を作成しましょう。専門用語はなるべく避け、イラストやフローチャートで手続きの流れを示すと理解が深まります。期限や提出書類の注意点も明記することが大切です。
年末調整シーズン前の「社内周知」がカギ
年末調整開始後に問い合わせが集中するのを避けるため、秋頃までに従業員への周知を徹底しましょう。メールや社内掲示板、説明会など複数の手段を活用し、早めの情報提供で従業員の手続きミスや混乱を減らすことが、担当者の負担軽減につながります。
特に今年は、2025年10月からポイント付与の廃止という制度変更があるため、駆け込み需要が予測されています。この点の告知に加え、「年末調整ではふるさと納税の控除ができない」ことも合わせて周知することをおすすめします。

▼BODのマニュアル作成・管理代行サービスなら、マニュアルのプロが対応いたします!▼

年末調整代行+問い合わせ対応の外部化で効率UP
■ 年末調整シーズンの担当者負担は想像以上に大きい
年末調整の時期は、ただでさえ手続きや確認作業が集中します。そこに、ふるさと納税をはじめとする各種控除についての質問が相次ぐことで、問い合わせ対応に多くの時間が割かれがちです。結果として業務が属人化し、担当者の負担は増す一方。ミスや対応の遅れといったリスクも高まりやすくなります。
■ 業務効率化の鍵は「問い合わせ対応の外部化」
こうした負荷を軽減する手段として注目されているのが、問い合わせ対応や一部業務の外部委託です。対応が分散・標準化されることで属人化を防ぎ、担当者が本来の業務に専念できる体制が整います。
例えば、以下のようなサービスが有効です。
●年末調整代行サービス:手続きの一部または全体をアウトソースし、専門スタッフに対応を任せる
●マニュアル作成代行サービス:よくある質問や案内文の整備を支援し、従業員からの重複質問を削減
●コールセンター代行サービス:専用のコールセンターを設置し、問い合わせ窓口を専門スタッフが対応
これらを活用すれば、問い合わせ対応や事務処理に追われる時間を減らし、確認・管理といった重要業務に集中できるようになります。結果として、ミスや遅延の防止につながるほか、従業員からの信頼感や満足度の向上にも寄与します。
外部サービスの導入を検討する際は、10月〜11月のピーク時に慌てて動くのではなく、早めの準備が鍵になります。 制度変更の影響もある今年は特に、業務の見直しやサポート体制の強化が求められます。
「人手が足りない」「時間がない」を言い訳にしないために── 。
プロの力を借りるという選択肢が、年末調整を乗り切る現実的かつ効果的な手段となるはずです。
BODの「年末調整代行サービス」
”手間がかかる業務”は、お任せください!
年末調整における各種申告書のチェックやデータ作成、不備・督促対応やファイリングなど、毎年スポットで発生する年末調整業務を代行します。電子化のデメリットでもある「システムの導入準備」や「従業員への周知」についてもサポートいたしますので、安心してご相談ください。
【すでに導入いただいている企業様よりいただいた声】
「年末調整を一任したおかげで、コア業務に注力する時間を確保できました」
「法改正への対応時間も削減され、スケジュール通りに年末調整を完了できました」
合わせて、以下のサービスもどうぞ検討ください!