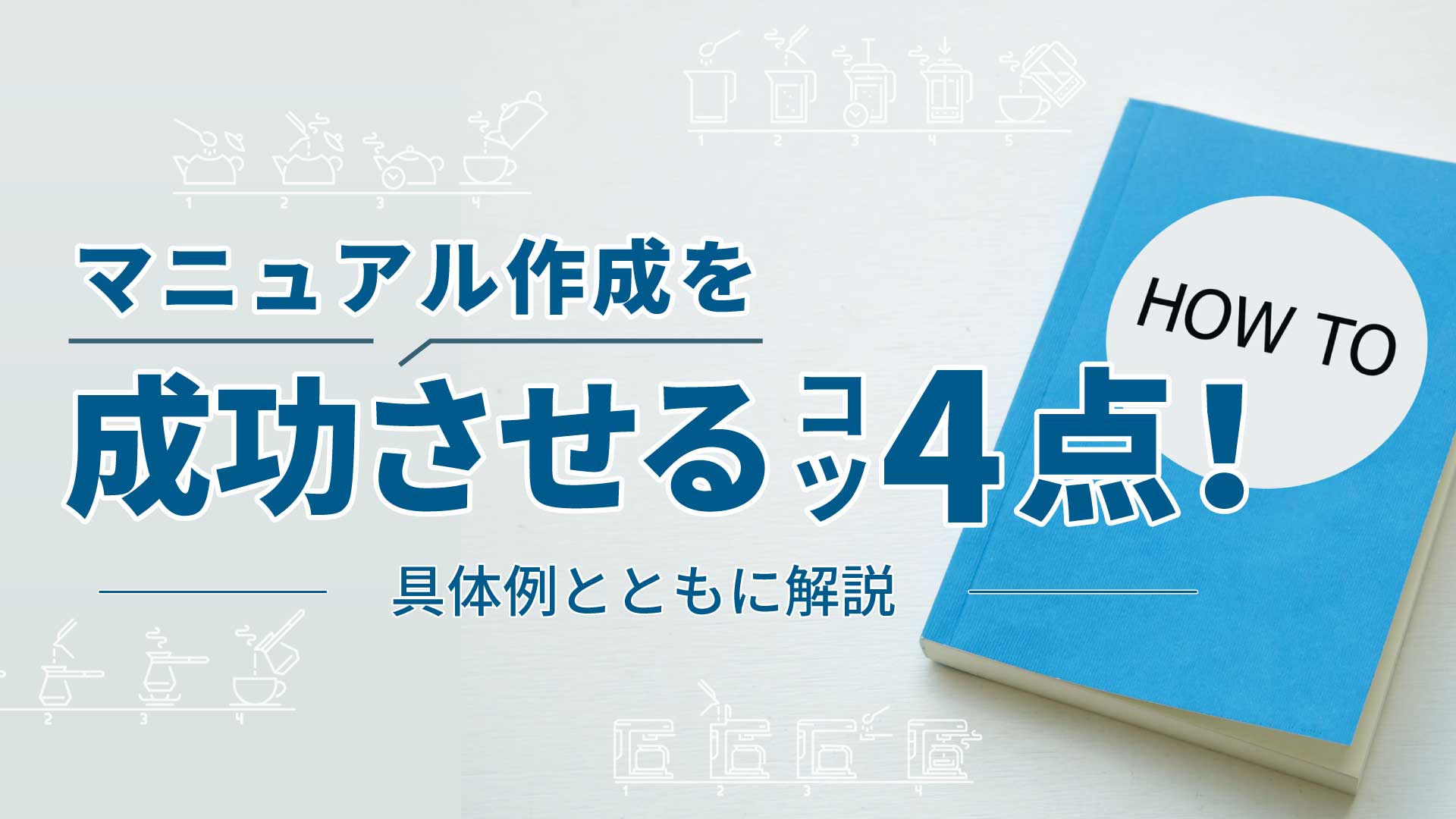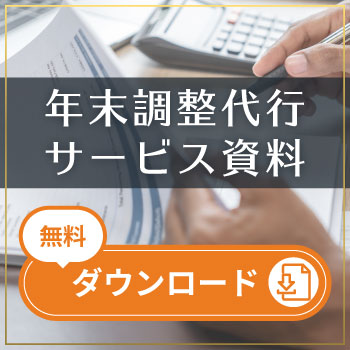マニュアル作成でこんなお悩み、ご経験はありませんか?
「上司や先輩に業務のやり方を教えてもらったら、マニュアルを作っといて!と言われた」
「せっかく一生懸命作ったマニュアルが分かりづらいと言われた」
「マニュアルを作っておいたのに、直接質問されたりして問い合わせが多い」
このようなお悩みをお持ちの方に、本記事では「マニュアル作成のコツ」について分かりやすく解説します。
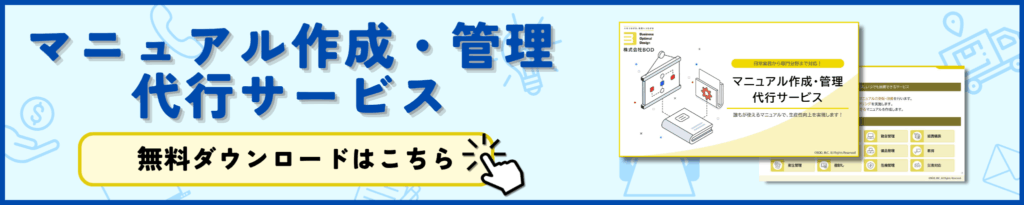
分かりやすいマニュアルづくり
結論を先にお伝えすると、マニュアル作成を成功させるコツは、ずばり以下の4点です。
【1】読み手・用途・閲覧シーン・ゴールを明確にする
【2】より分かりやすいマニュアルになるよう、構造・構成を決め、表現や文章を工夫する
【3】実際にマニュアルを見て作業し、不具合箇所を検証、改善する
【4】作成スケジュール・担当者を決め、最初から100点を目指さない
では、次の項から一つひとつ解説していきましょう。

マニュアルの役割・作成する目的とは?
マニュアル作成を始める前に、マニュアルの役割・目的を意識しておくことが大切です。
なぜなら、何のためにマニュアルを作るのか、目的がブレたまま作成してしまうと、マニュアルを使う人が混乱する可能性があるからです。
「マニュアルは何のために作成するのでしょうか?」
誰かに業務や作業手順を伝える、困ったときに対処法を見る、社内業務の引き継ぎ…など、いろいろと思い浮かぶと思います。マニュアルの役割、作成する目的の根本は、「”決められたやり方” で、 ”すべての人” が、 ”同じように” 作業できること」にあります。これこそ、手間をかけてもマニュアルを作成するメリットと言えますね。
企業活動においては、利益を上げることが求められます。限りある時間を有効に活用し、人的ミスやロスを減らして、いかに最大限の成果を上げるかがカギになります。言い換えれば、業務効率を上げて、どれだけ生産性を高められるか、ということです。
日々の業務の中で、必要なタイミングでマニュアルを見たときに、決められたやり方ですべての人が同じように作業できるようになれば無駄な時間が減って仕事の生産性が向上し、結果的に売上、利益が向上することにつながります。
誰もが使えるマニュアルで、生産性向上を実現! BODの「マニュアル作成・管理代行サービス」
マニュアル作成でよくある落とし穴
マニュアル閲覧者の困りごと
ここで、マニュアルを使う人、読み手側の視点に立ってみましょう。
何か業務や作業をする際にマニュアルを見ようとしたとき、こんな経験はないでしょうか?
- どのマニュアルを見ればよいのか分からない
- 手順書に書いてある内容・用語の意味が分からない
- ポイントだけを知りたい・不明点を解消したい
- 実際にやってみるとうまくいかない

これらの状況はなぜ起こるのでしょうか。それは、マニュアル作成にはよくある落とし穴、つまり‟失敗パターン”があり、多くのマニュアルがその落とし穴にはまってしまっているからです。
マニュアル作成の失敗パターン
「”決められたやり方” で、 ”すべての人” が、 ”同じように” 作業できる」マニュアルを作るためには、失敗パターンをしっかりと理解する必要があります。失敗する理由はたくさんありますが、マニュアル作成の手順に沿ってまとめると以下の4点です。
【マニュアル作成の失敗パターン】
1.作成するマニュアルの設定があいまい
2.マニュアルの構造・公正が不適切
3.文章・表現が不適切
4.作成して終わりになっている
作成するマニュアルの設定があいまい
マニュアルは、読み手(閲覧者)がいてこそ使われるもの。つまり、閲覧者と閲覧するシーンの具体的な想定が最も重要です。この想定があいまいだと、読み手は全体像がつかめず、マニュアルを見ても業務内容が伝わらないことがあります。

■カレーライスの作り方をマニュアル(=レシピ)化する例で考えてみましょう。
レシピを見る人が、カレーを作ったことがないのか、頻繁にカレーを作っていてスパイスからこだわって作りたいのかによって、準備する食材や流れは全然変わってきますよね。まずは対象となる読み手が‟どの段階、レベルにある人なのか”を想定することが重要です。
また、どんなシーンでレシピを見るのか、どんな媒体で(紙なのか動画なのか)見るのかによっても設定は変わってきます。自宅でカレーを作る場合は、モバイル端末で動画を見ながらでもいいですが、レストランの厨房でカレーを作る場合では、忙しいので動画をゆっくり再生している時間はありません。むしろ分からないところだけを紙でさっと確認するほうが理にかなっている場合もあります。
マニュアルの構造・構成が不適切
業務や作業の流れが上手に構成されていないと、頭に入ってきづらく誰もが同じように作業を進めることは困難です。作業の順番がそもそも間違っていたりするとミスやロスにつながってしまうため、作業の流れが正確かどうかを見直すことが重要です。

■カレーライス作りの例で言えば、火が通りやすい食材から炒めてしまったり、ルーが煮立ってからご飯を炊き始めたりするのでは、非効率ですよね?
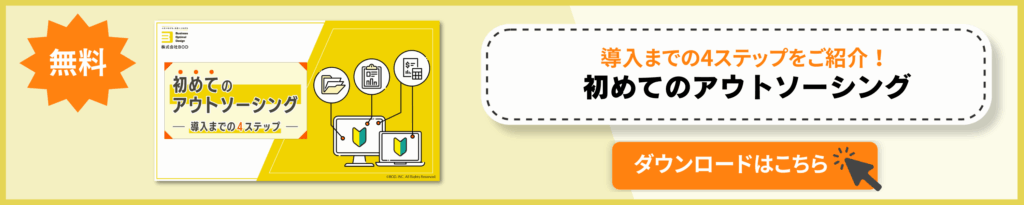
文章・表現が不適切
マニュアルに、行うべき作業内容は網羅されているものの、どこが重要か分かりづらい場合も読み手には伝わりづらいものとなります。例えば、単なるテキストだけで表現している場合、人によって理解度に差が出てしまい、同じマニュアルを見て作業しても、成果物にはばらつきが出てしまうことがあります。

■カレー作りの例で言えば、例えばレシピの肝心な部分が「バター20g」で食材を炒めることだった場合に、このバター20gが強調されていないと、ほかの情報に埋もれてしまって見落す可能性もあるでしょう。また、「フツフツと泡が出るまで煮立たせる」と文章で書かれていた場合、人により「フツフツ」の基準は違います。
このように文章で伝えるのがそもそも難しい場合は、画像や動画を適切に使うことも検討しなければなりません。
作成して終わりになっている
マニュアル作成で失敗する理由のうち、一番見落とされがちなパターンが、マニュアルを‟作って終わり”になってしまうことです。下手をすると、そのマニュアル作成者自身を含めて、誰もマニュアルを見ながら作業したことがない、というケースもあります。これでは、「マニュアルを作成すること」自体が目的になってしまっていて、何のためのマニュアルなのか分かりませんね。

この状態は属人化の原因にもなり、期待される品質で”すべての人” が ”同じように”作業を行うことは難しいでしょう。一度作ったマニュアルは、実際にマニュアルを見て作業し、不具合箇所を検証し、改善することが重要です。検証は定期的に行いましょう。作業内容が変更になったときは、その都度内容を更新することも大切です。
マニュアル作成を成功させるコツ4点
マニュアル作成の失敗パターンをご理解いただいたところで、分かりやすいマニュアルの作成方法を、改めてご説明します。ポイントは冒頭でも述べたとおり、4点あります。
【1】読み手・用途・閲覧シーン・ゴールを明確にする
【2】より分かりやすいマニュアルになるよう、構造・構成を決め、表現や文章を工夫する
【3】実際にマニュアルを見て作業し、不具合箇所を検証、改善する
【4】作成スケジュール・担当者を決め、最初から100点を目指さない
読み手・用途・閲覧シーン・ゴールを明確にする
マニュアルは、作成する前の想定・準備が大切です。まずは読み手と閲覧シーンをできるだけ明確にしましょう。明確に定義すべきは、以下のポイントです。
- 利用者・タイミング(誰が・いつ見るのか)
- 対象・範囲(何を・どこまでつくるのか)
- 場所・手段(どこで・どうやって見るのか)
- ゴール・達成基準(どうなればOKか)

どのように決めたらよいか、事業ごとの例を表でまとめてみました。
マニュアルを作成する前には、表に整理してみるとブレが少なくなり、おすすめです。
| 事業内容 | 利用者・ タイミング |
対象・範囲 | 場所・手段 | 達成基準 |
|---|---|---|---|---|
| 誰が・ いつ見るのか |
何を・ どこまでつくるのか |
どこで・ どうやって見るのか |
どうなればOKか | |
| 店舗運営 | 店舗スタッフ 研修・通常業務時 |
店舗運営関連 ※規約やルールに関するものは対象外とする |
店舗 タブレット |
本部へ確認することなく業務遂行できる |
| 製造 | 各レーン担当者 定期教育時 |
クレームの状態、 原因・対策を記録する |
工場内 モバイル端末/紙 |
クレームの概要を理解する |
| 小売 | 配送委託先スタッフ 研修・商品納品時 |
配送先の個別ルール (納品場所・特記事項など) |
事務所/車中 モバイル端末 |
ミス・トラブルなく納品を完了する |
誰が、いつどんなときに使うものか?、何をどこまで説明するものなのか?、どこでどうやって見るものか?、どうなればOKか? これらを明確にすることがポイントです。
構造・構成を決め、表現や文章を工夫する
◆ 【構造・構成】 ◆
業務とは「動作」または「作業」の集合です。ひとつのマニュアルの中で対象とする範囲は「ひとつの業務」または「ひとつの作業」とし、ステップ形式になっていると分かりやすくなります。ステップの基本単位はひとつの動作(指示)になっていると良いでしょう。
例)マニュアル「レジで現金会計を行う」
Step 1:レジへ入金する
Step 1-1:現金を受け取る
Step 1-2:紙幣を揃える
Step 1-3:受口に投入する
Step 2:レジからお釣りを出す
Step 2-1:モニターを目視する
Step 2-2:トレーを開く
Step 2-3:現金を取り出す

より分かりやすいマニュアルになるよう構成を決め、表現・文章を工夫すること。1ステップがあまりにも長くなる場合は分割することを考えましょう。
◆【 表現・文章】 ◆
文章で書く場合、以下の点に気をつけると良いでしょう。
- 1文は50文字以下
- 「など」を多用しない
- 専門用語や略語には説明や補足の記載を忘れずに
- 用語や表記は一貫性を持たせる
- あいまいな動詞ではなく、意味が限定される動詞を選ぶ
| あいまいな例 | 良い例 | |
| 例1 | 提出書類を確認する | 提出書類に不足がないか確認する 各項目に入力漏れがないか確認する |
| 例2 | 不良品を処理する | 不良品を見つけたら回収ボックスへ入れる |
| 例3 | つまみを調整する | 目盛りが0になるまでつまみを右に回す |
| 例4 | 在庫を管理する | 棚卸をし、管理表と相違ないか比較する |
| 例5 | 必要に応じて入力する | A列とB列の値が同じ場合にC列に入力する |
文章では伝わりづらい場合は、可能な限り画像や動画を添えられると、マニュアルを見て実際に作業する際の再現性がより高くなります。
実際にマニュアルを見て作業し、不具合箇所を検証、改善する
マニュアルとは、それを見た人が同じように業務・作業できるようにするためのものです。マニュアル作成が完了したら、そのマニュアルの対象と想定している現場の従業員に、実際にその通りに作業してもらいましょう。

実際に作業してもらって、うまくいかなかったり、つまづいたりしたところは情報を共有し、検証しながら直していきます。そうすることでマニュアルの質・価値は上がっていきます。
作成スケジュール・担当者を決め、最初から100点を目指さない
マニュアル作りとは、し始めるとキリがないものです。たくさんある業務のどこを切り出してどう構造化し、分かりやすく表現するか? これを突き詰めて網羅的にしようとすると膨大な時間がかかってしまいます。
そのため、「マニュアルを作成・公開・周知・改善する」という一連のスケジュールを誰が担当するのかとともに、しっかりと定めましょう。
また、マニュアルとは運用しながら改善していくことで、確実に品質を上げることができます。最初から100点を目指さず、改良を重ねていくことこそ、マニュアル作成を成功させるコツと言えますね。
誰もが使えるマニュアルで、生産性向上を実現! BODの「マニュアル作成・管理代行サービス」

マニュアル作成は「手段」
マニュアル作成のコツについて、失敗する理由を踏まえて解説してきました。注意していただきたいのは、マニュアルはあくまで目的達成や課題解決のための「手段」だということ。「マニュアルを作成すること」それ自体が目的やゴールになってしまわないように気をつけましょう!
さらにマニュアル作成を効率化するには?
ここまでご説明してきたコツを参考にマニュアルを作成すれば、本来の目的を達成できるマニュアルに近づけることができるはずです。それでも、マニュアルの読み手(閲覧者)が理解しやすいマニュアルを1から作るのはなかなか難しいもの。
そんなときには、BODの「マニュアル作成・管理代行サービス」がおすすめです!今回ご紹介した失敗しないコツ・ポイントを踏まえた、マニュアル作成をより効率的に行えるサービスです。
「マニュアル作成は手間がかかってやっぱり面倒…」という方は、ぜひご検討ください! ”決められたやり方” で ”すべての人” が ”同じように” 作業できる業務マニュアルを実現します!
BODの「マニュアル作成・管理代行サービス」
誰もが使えるマニュアルで、生産性向上を実現!
業務マニュアルの作成、修正・更新、どのフェーズでもマニュアル作成のプロに依頼できるサービスです。人事労務や給与計算等の事務作業、飲食業での接客や衛生管理、危機管理や災害対応まで、幅広い分野のマニュアル作成を代行します。
誰が見ても分かりやすく使いやすい、再現性の高いマニュアルづくりなら、BODにお任せください!