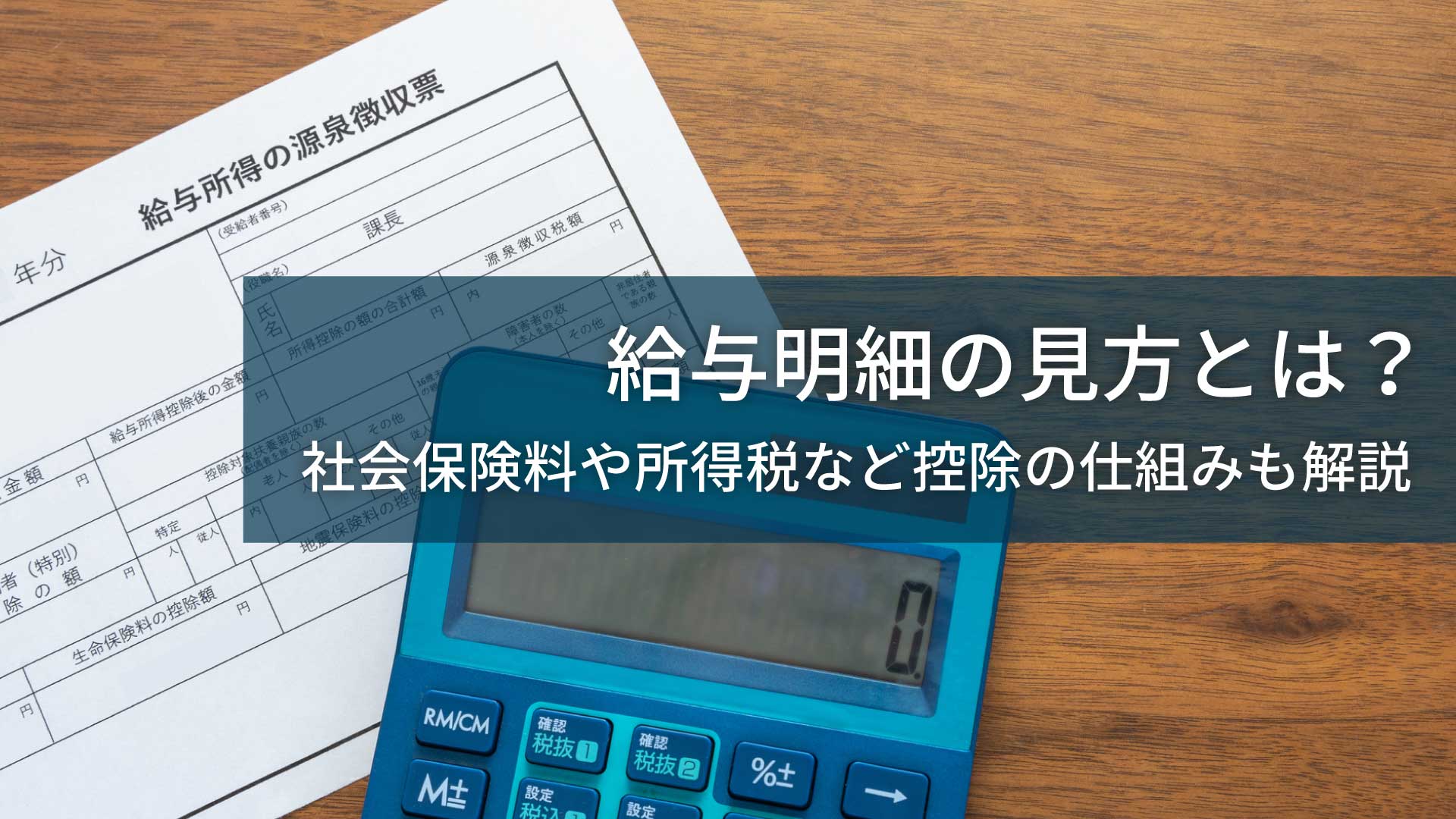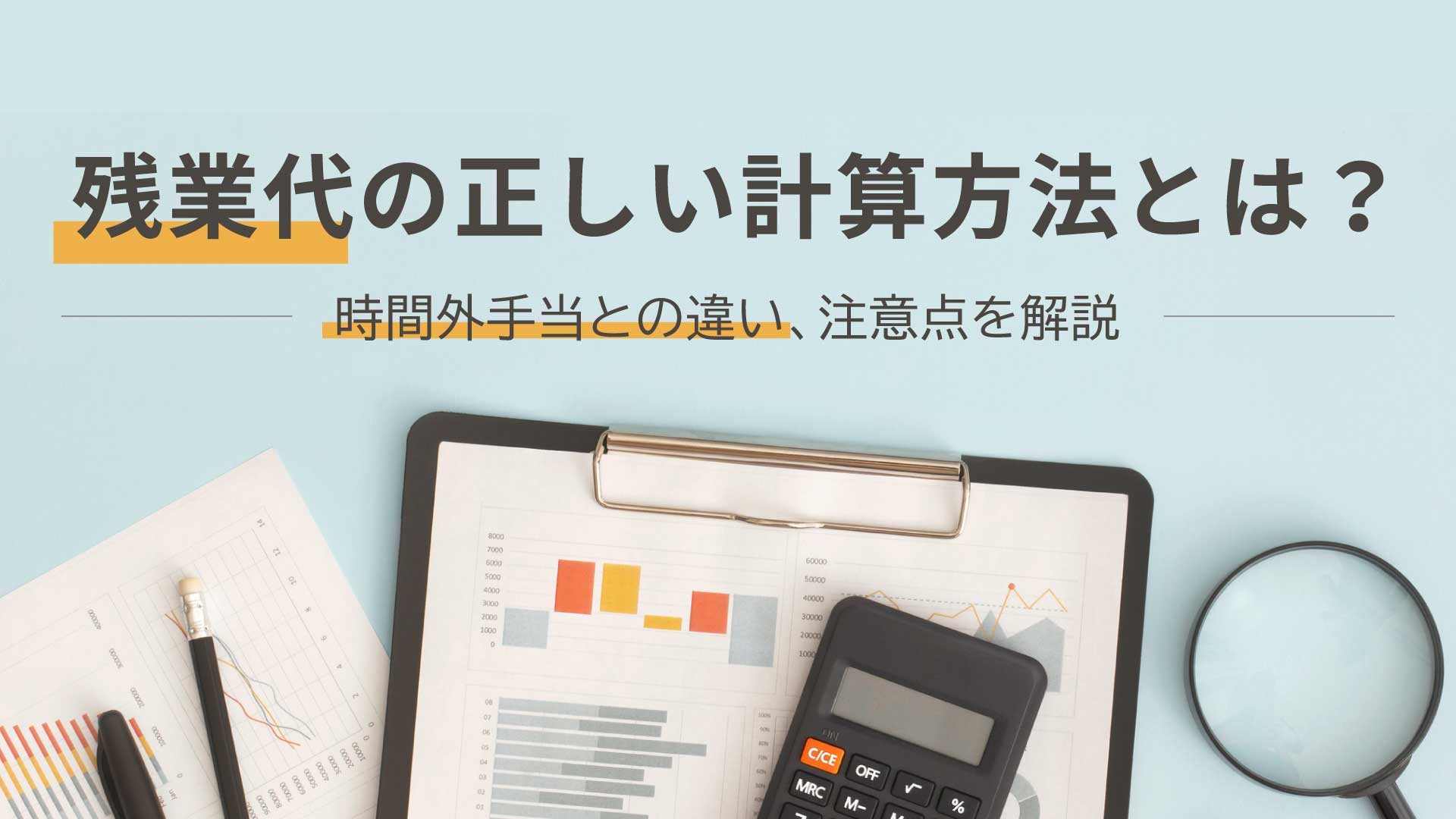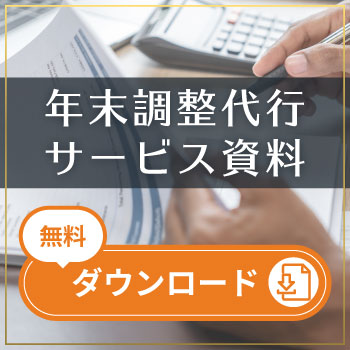給与が支払われる際に受け取る「給与明細書」。毎月もらうけど具体的な記載事項はよく分からない、手取りってこんなに減るの?など、疑問を感じながらそのまま…という方、多いのではないでしょうか。この記事では、給与明細の見方や控除金額の計算方法について、項目ごとに解説します。
給与明細書に記載される項目
「給与明細書」とは、支払われる給与の根拠となる情報が記載された書類のことです。
労働基準法では、給与明細の交付に関する定めはありません。しかし、所得税法第231条で「給与を支払う者は給与の支払を受ける者に対し、支払明細書を交付しなくてはならない」と定められています。そのため、会社は給与支払い時に給与明細の交付が必要です。以下の項目で構成されています。
勤怠

支給

控除

差し引き支給額
差引支給額は、実際に従業員に支払われる給与額です。
総支給額から税金などの控除額を差し引いた額で、一般的に「手取り」と呼ばれている金額のことです。

□・・・実際に受け取る金額(総支給合計-控除合計)
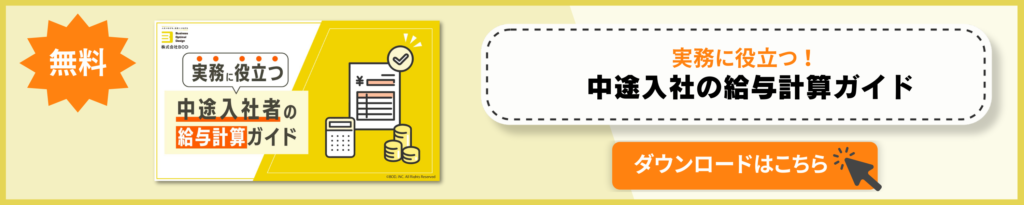
各項目でチェックするポイント
ここからは、「勤怠」「支給」「控除」の見方について、それぞれ確認していきましょう。
「勤怠」の見方
「勤務日数」や「欠勤」「有給」「残業」などの日数や時間が示される欄です。
ここで注意が必要なのは集計間違いが起こりやすい「残業時間」の項目です。1日あたりの残業時間が数分だとしても1カ月単位で見れば、大きな数字になります。勤怠管理システムなどで勤務時間が自動管理されていないようであれば、日頃から出勤時間と退勤時間をメモしておき、実際の給与明細に記載された「残業時間」と照らし合わせて確認することをおすすめします。

「支給」の見方
「基本給」のほかに「役職手当」「家族手当」など各種手当が明記されている欄です。
支給項目で、特に重要なのが時間外労働(残業手当)や休日労働(休日出勤手当)、深夜労働(深夜手当)に対する割増賃金です。
残業代の計算方法、割増賃金率については、こちらの記事をご覧ください。

「控除」の見方
給与明細の「控除」とは、給与からあらかじめ引かれている金額のこと。「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「所得税」「住民税」など、給与から差し引かれる項目が記されています。
ここでは「社会保険料」「雇用保険料」「税金」の3つに分けて、控除の概要を詳しく解説します。

【社会保険料】
社会保険料とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の総称です。これらは、会社と半分ずつ負担し、給与明細には自己負担分が記載されます。
・健康保険料率は、加入している健康保険(組合健保・協会けんぽ・各種共済組合)と、住んでいる地域によって異なるため、自身の加入している健康保険組合のホームページを確認してみましょう。
・厚生年金保険とは、会社員として働く人が加入する公的年金のこと。自己負担額は、下記の計算式で求めることができます。
標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2 = 厚生年金保険料(自己負担額)
標準報酬月額は、下記の月額表に当てはめて算出できます。
出典)日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)」
・介護保険料は40~64歳の人のみが負担するため、40歳未満の方の給与明細では空欄になります。
・給与計算担当者が退職…。属人化していたため対応できる人がいない
・独自の給与計算ルールがあり、業務が非効率的
こんなお悩みには、BODの「給与計算代行サービス」をおすすめします!
→→→ サービス資料を無料でダウンロードする
【雇用保険料】
雇用保険料は、失業時に給与の代わりとなる「失業等給付」を受けるための保険です。
「雇用保険料率」は、年度や事業によって異なります。2023年度の一般の事業の雇用保険料率は15.5/1,000です。そのうち、9.5/1,000は会社負担で、労働者の負担は6/1,000です。よって、給与額×0.006が雇用保険料の自己負担額になります。
出典)厚生労働省:「令和5年度雇用保険料率のご案内」
【所得税・住民税】
・所得税はその年の1月1日から12月31日の間に得た所得に対して課税される国税です。社会保険料等を控除した後の給与に応じて計算されます。本来、所得税額は1年単位で計算しますが、会社員の場合は毎月の給料から概算で源泉徴収されます。過不足は、12月の給料を受け取るときに調整が行われます(年末調整)。
・住民税は従業員が住民票のある市町村や、都道府県に納める税金のこと。前年の給与に基づき、6月から翌年5月にかけて徴収されます。会社員であれば、住民税は給与から控除され、会社が代わりに納付するのが一般的です。これを「特別徴収」といいます。
所得税
- 1月から毎月控除(仮払い)
- 12月の年末調整で税額決定
- 精算
住民税
- 1月~12月の所得で税額決定
- 翌年6月から毎月分割後払い
- 翌々年5月に納付完了
社会人1年生は前年の給与がないので、住民税が引かれることはなく空欄です。社会人2年目の人も、まだ住民税の全額負担ではありません。前年の所得(社会人になった4月から12月まで)に対して住民税がかかるためです。住民税が全額負担になるのは社会人3年目からです。
給与明細は大切な証明書
毎月、給与明細書を見ていても、数字の詳細までは詳しく確認していないという方は多いのではないでしょうか。給与計算にまつわる法改正も頻繁に行われますが、各項目の内容を知っておけば、急に数字が変わったとしても落ち着いて対処できますね。
給与明細は働いた日数や時間の記録だけでなく、収入を証明するものとして使うことができます。例えば、未払いの給与や残業手当が判明し、それを請求する際には証拠として利用可能です。また、「過去に年金の未納分があった」などと確認を求められた際にも、給与明細があれば、証明書代わりになるでしょう。
そのため、給与明細をもらったらすぐに捨てるのではなく、一定期間保管しておくといざというときに安心です。念のため、毎年もらえる源泉徴収票も一緒に保管しておきましょう。
BODの給与計算代行サービスなら…
勤怠集計、給与・賞与の計算、給与振込データ作成、給与明細作成など、給与計算にかかる一連の作業をアウトソーシングできます。給与計算担当者の負担を軽減するためにも、ぜひご検討ください。
人事労務システム導入後のシステム連携もお任せください!
人事労務システムを導入したとしても、そこで業務が完全に完結するわけではありません。
その先の「会計情報との連携」や、それらに関わる全ての業務が円滑に進むよう、
システム同士の連携や運用支援まで行います。
業務改善、最適化も含めた給与計算のアウトソーシングプランをご提案しています。
給与計算代行サービスはこちら