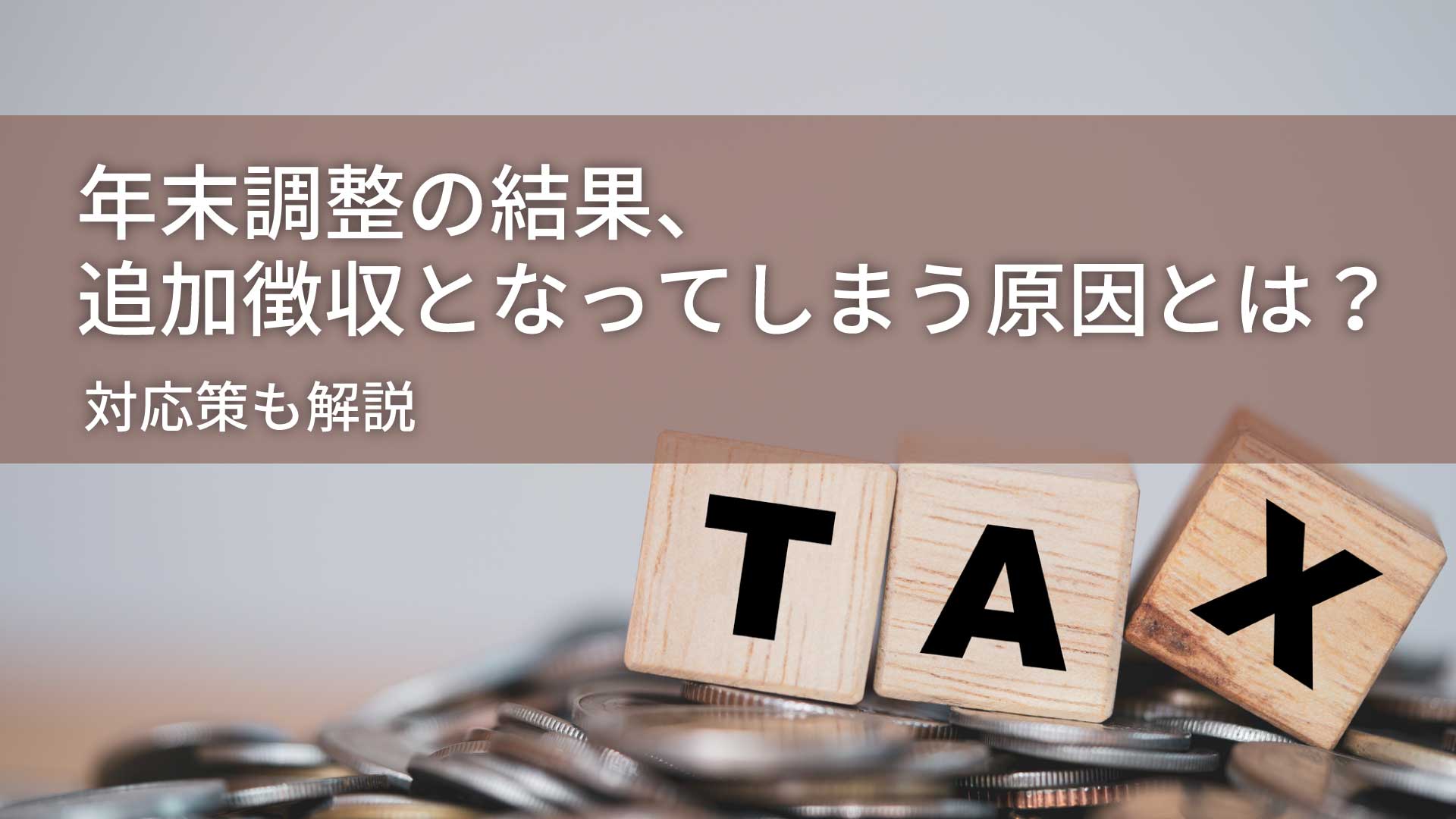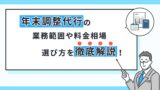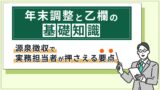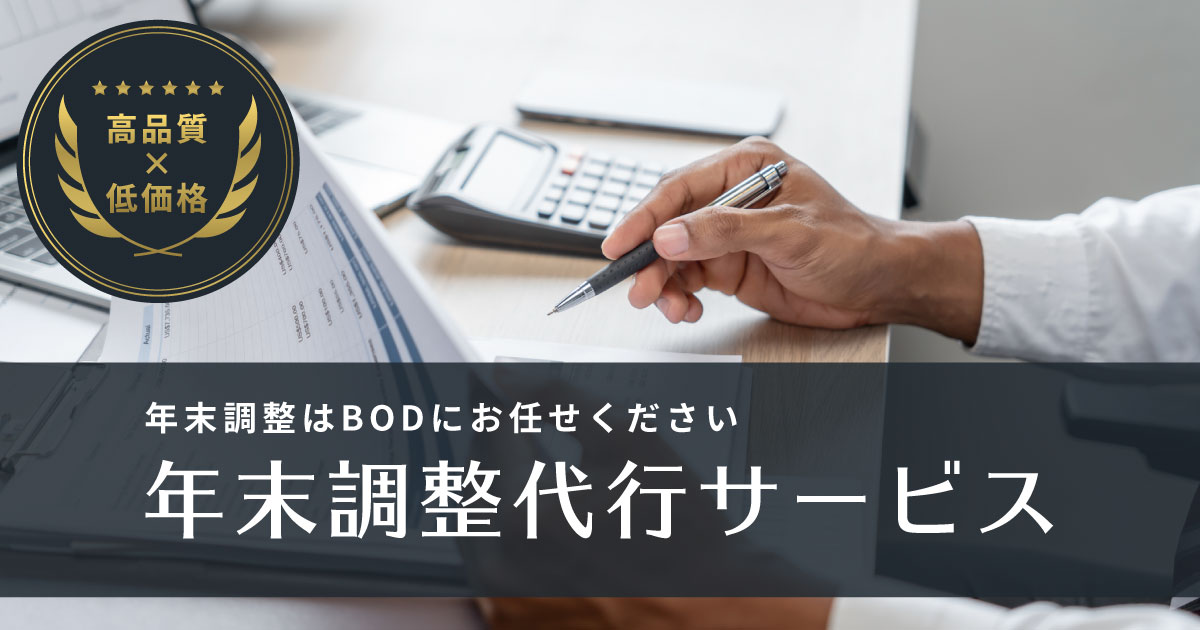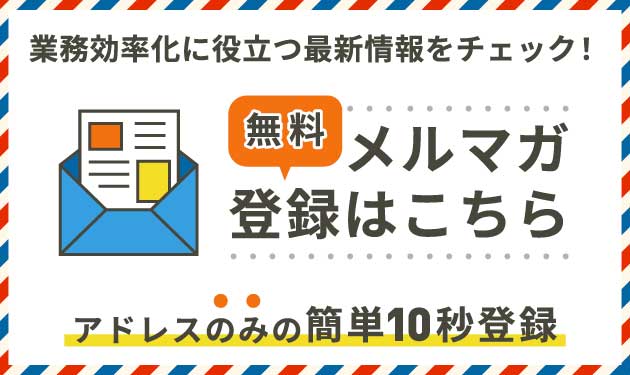年末調整では「税金が戻る」イメージが一般的ですが、人によっては「追加徴収」が発生することもあります。この記事では、追加徴収が起きる仕組みや計算方法、主な原因と対応策、さらに確定申告が必要となるケースまで、流れに沿ってわかりやすく解説します。
▼BODの年末調整代行サービスなら、運用体制に合わせて柔軟に対応! WEB/書面、工程選択もOK!▼
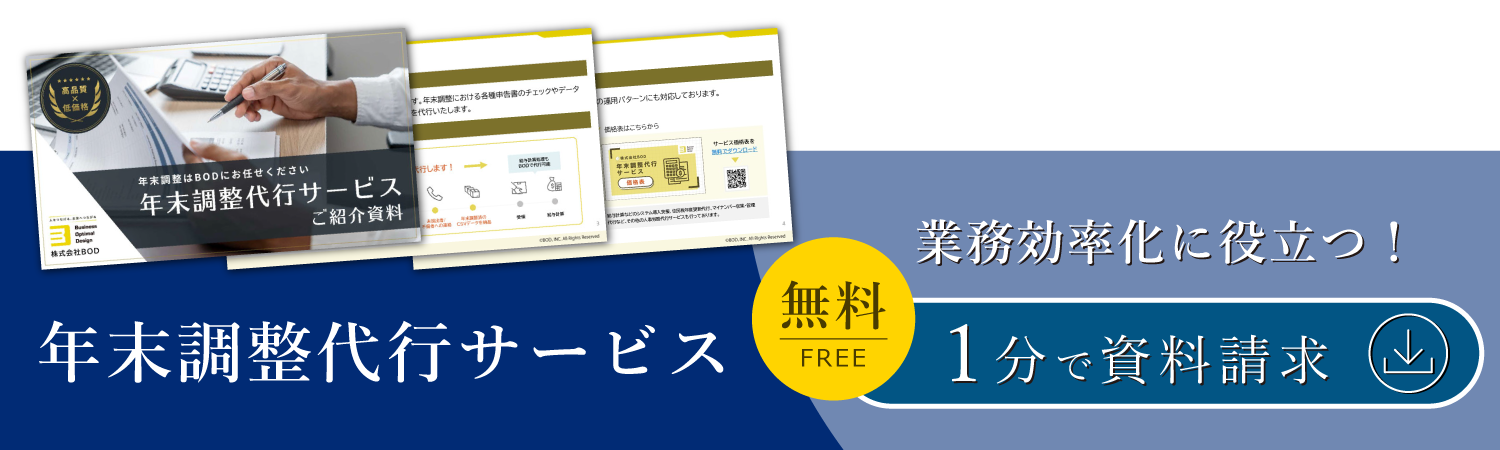
年末調整の追加徴収とは
年末調整とは
「年末調整」とは、1年間の給与総支給額と各種控除をもとに、正しい所得税額を再計算し精算する手続きです。毎月の給与で源泉徴収された税額と、最終的な税額との差を調整し、過不足をなくすことが目的です。
「追加徴収」の仕組み、「還付金」との違い
年末調整は会社が従業員に代わって行い、精算結果は12月の給与明細などで「年末調整還付・追徴額」として反映されます。
| 追加徴収 | 正確な所得税額を算出した結果、源泉徴収していた税額よりも、最終的な税額が多い場合に発生。差額を給与から徴収します |
| 還付金 | 源泉徴収していた税額の方が多かった場合に、差額分が従業員へ返金されます |
多くの従業員は還付になりますが、控除や所得の状況によっては追加徴収になるケースもあります。
「追加徴収=ミス」ではなく、あくまでも精算結果として正しい処理
実務担当者は、従業員から問い合わせを受けた際に説明できるよう仕組みを理解しておくことが大切です。
「追加徴収」と「追徴課税」の違い
追加徴収と似た言葉に、「追徴」、「追徴課税」がありますが、意味と使われる場面が異なります。
| 追加徴収 | 年末調整で所得税を精算した結果、源泉徴収額が不足していた場合に給与から差額を徴収すること |
| 追徴(追徴課税) | 申告漏れや無申告などのミス・違反に対して課される税金を指します |
追徴課税は、税務署からの指摘により課されるペナルティー的な性質のもので、過少申告加算税や延滞税が上乗せされる場合もあります。
年末調整での「追加徴収」は、あくまで正しい税額に精算する通常の処理
一方の「追徴課税」は、税務違反への制裁と覚えておくと区別しやすいでしょう。
▼毎年の年末調整業務、人事労務ご担当者には負担が大きくのしかかります。
代行サービスの価格表を参考に、外部委託を検討してみてはいかがでしょうか。▼

追加徴収の計算方法
年末調整で追加徴収が発生する場合、基本的な計算の流れは以下の通りです。
(1)年間の給与総額を算出
1年間に支払われた給与・賞与の合計を計算します。
(2)各種所得控除額を算出
扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、適用できる控除を算出します。
(3)給与総額から控除額を差し引く
(1.給与総額 −2.所得控除額)で課税対象額を求めます。
(4)所得税額を算出
3.で算出した課税対象額に応じた税率を当てはめ、年間の所得税額を算出します。
(5)源泉徴収済み額との差額を確認
毎月の給与からすでに源泉徴収されている税額と比較し、差額を追加徴収または還付として処理します。

年末調整での追加徴収は、年間ベースで正しい税額に調整するための処理です。給与明細単位ではなく、1年間の合計で精算することが重要です。
より詳しい計算方法や具体的な手順については、以下の記事内で解説しています。合わせてご確認ください。
年末調整で追加徴収される原因とは
給与所得者の年末調整で追加徴収が発生する原因となる主なケースについて、整理します。
扶養親族が減った場合
給与や賞与の源泉所得税は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告された扶養親族の人数を基に算出されます。年の途中で扶養家族が減った場合に、追加徴収される原因となるケースがあります。
・扶養親族が多いほど税額は低く、少ない(または0人)ほど高くなります。
・年の途中で扶養親族が減った場合、本来より多く税額を納める必要が出ます。
【具体例】
配偶者 + 子ども2人(大学生・中学生)家族の場合
扶養親族 =3人
→ 4月に大学生の子が就職し扶養から外れる
→ 扶養親族は2人に

年末調整は12月31日時点の状況を基に行うため、1年間を通して「2人」として精算
4月まで扶養家族3人として少なく徴収されていた税額との差額が追加徴収として発生する可能性があります。
【ポイント】
年末調整は12月31日時点での状況を基に、年間ベースで税額を精算します。
引用)国税庁「令和7年分 源泉徴収税額表 」
給与や賞与の支給額が増えた場合
給与や賞与が年の途中で増える場合も追加徴収が発生します。
【具体例】
・役職手当の追加 ・人事異動による給与増額
・転職後の給与差額 ・会社や個人の業績に応じた賞与(ボーナス)の増額
【理由】
所得税額は「年間給与・賞与の概算」に基づき画一的に計算されています。一旦仮の税額で徴収するため、実際に支給された金額が概算より多い場合、差額分の税額が追加徴収として調整されます。
その他、控除が減少した場合
控除額が減ることも、源泉徴収額よりも本来納めるべき税額が大きくなり追加徴収の原因になります。主なケースは以下の通りです。
- 「保険料控除」
生命保険の解約や掛け替えによる減額で控除を適用できなくなった
地震保険や社会保険など保険料控除の適用がなくなった - 「小規模企業共済等掛金控除」
iDeCo(イデコ)の掛け金を減額したため控除額が減った - 「障害者控除」
障害の程度が軽くなり控除を受けられなくなった
【注意点】
年末調整書類の添付漏れが原因で控除が適用されず、追加徴収になることもあります。生命保険控除証明書など、必要書類の添付を必ず確認しましょう。控除を適用したい場合は、年末調整後でも確定申告で修正可能です。
▼社会保険料の仕組みについて、手取り額変動のカラクリを解説する資料です。詳しくはこちら▼

追加徴収が多く発生したときの対策
年末調整の結果、追加徴収が多く発生した場合の具体的な対策について整理します。従業員への負担を軽減し、適切に対応することが重要です。
繰延承認申請の検討
追加徴収は、基本的に年末調整を行った月(通常12月)の給与から徴収されます。
しかし、12月分の税引後給与が通常月(1月~11月)の平均給与額の70%未満となる場合は、不足額の徴収を繰り延べることが可能です。
【繰延承認申請の手順】
(1)年最後の給与支給前日までに「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成
(2)勤務先の所轄税務署長に提出
(3)承認を受けることで、不足分の徴収を翌年1月・2月に分けて繰り延べが可能
引用)国税庁「年末調整による不足額徴収繰延の承認申請」
追加徴収の納税期日と特例
追加徴収された源泉所得税の納付期限は、原則として給与から徴収した翌月10日までです。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の事業者については、特例として年2回(7月・翌1月)にまとめて納付することが認められています。
【ポイント】
・事業者が対象要件を満たしているか確認する
・追加徴収が多く発生した場合は、労務担当者や税務署、専門家に相談
引用)国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
▼年末調整をスムーズに電子化するには、こちらの資料がおすすめです!▼

▼年末調整代行について必要な情報が完全網羅されています。こちらの記事をご覧ください。▼
追加徴収後に確定申告が必要になるケース
年末調整によって追加徴収が行われた後でも、場合によっては従業員本人が別途確定申告を行う必要があります。ここでは、主なケースと実務担当者が確認すべきポイントを整理して解説します。
給与以外の収入がある場合
年末調整は給与所得を対象に実施される手続きです。給与以外に雑所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得などがある場合には、年末調整のみでは税額精算が完結せず、確定申告が必要になります。
【具体例】
副業で得た報酬が「雑所得」として20 万円を超える場合、確定申告の義務があります。

2カ所以上から給与を受け取っている場合
複数の勤務先がある従業員では、年末調整を受けた主たる給与先以外の給与分は精算対象にならないため、年末調整を受けていない給与+その他の所得があると、確定申告が必要となる場合があります。
▼複数の勤務先があり、源泉徴収票に「乙欄」の記載があるケースについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
控除項目・申告内容に誤り・抜けがある場合
年末調整で扱われない控除(例えば医療費控除・寄附金控除など)を受ける必要がある、または控除申告に漏れ・誤記があった場合には、確定申告による修正が必要です。
【実務担当者向けチェックポイント】
・勤務先が複数ある従業員の状況を確認し、年末調整対象外給与がないか把握
・控除申告書類の抜け漏れ・誤記の有無を年末調整実施前にチェック
・確定申告が必要となるケースを従業員に案内し、案内資料や相談窓口を準備しておきましょう
▼給与計算に関する人気資料を3点まとめました。ご参考になれば幸いです。▼

追加徴収になっても適切に対応を
年末調整で追加徴収が発生すると、手取り額が一時的に減るため、損をしたように感じることもあるかもしれません。しかし、年末調整は給与所得者の1年間の税金を正確に計算して精算する手続きです。「還付」も「追加徴収」も、損得ではなく正しい税額の調整であることを理解しておくことが重要です。
実務担当者としては、追加徴収が発生する原因や対応方法を把握し、従業員への説明やフォローを適切に行うことがポイントです。
毎年大変な年末調整はBODにお任せください!
年末調整業務は毎年発生するスポット業務であり、書類チェックやデータ作成、不備対応、ファイリングなど、実務担当者の負担も大きくなりがちです。
BODの「年末調整代行サービス」なら、これらの業務をまとめて代行。WEB・書面どちらの運用にも対応し、従業員対応のフォローや提出書類の精査も含めて効率的に処理できます。
▼年末調整のお見積りはこちら▼