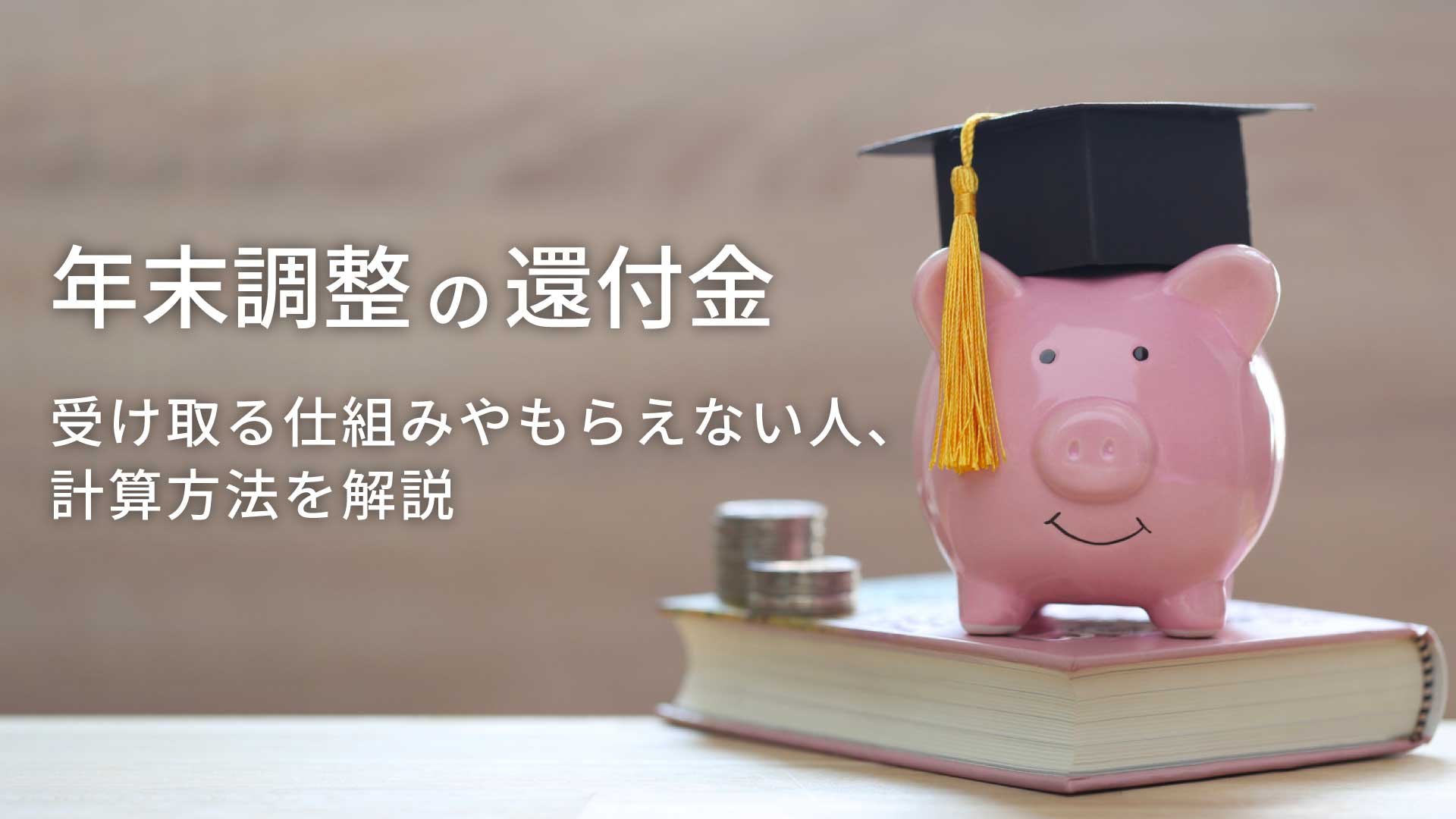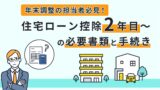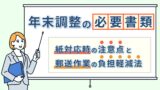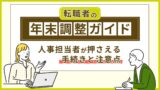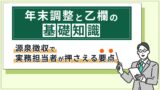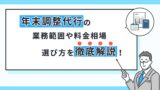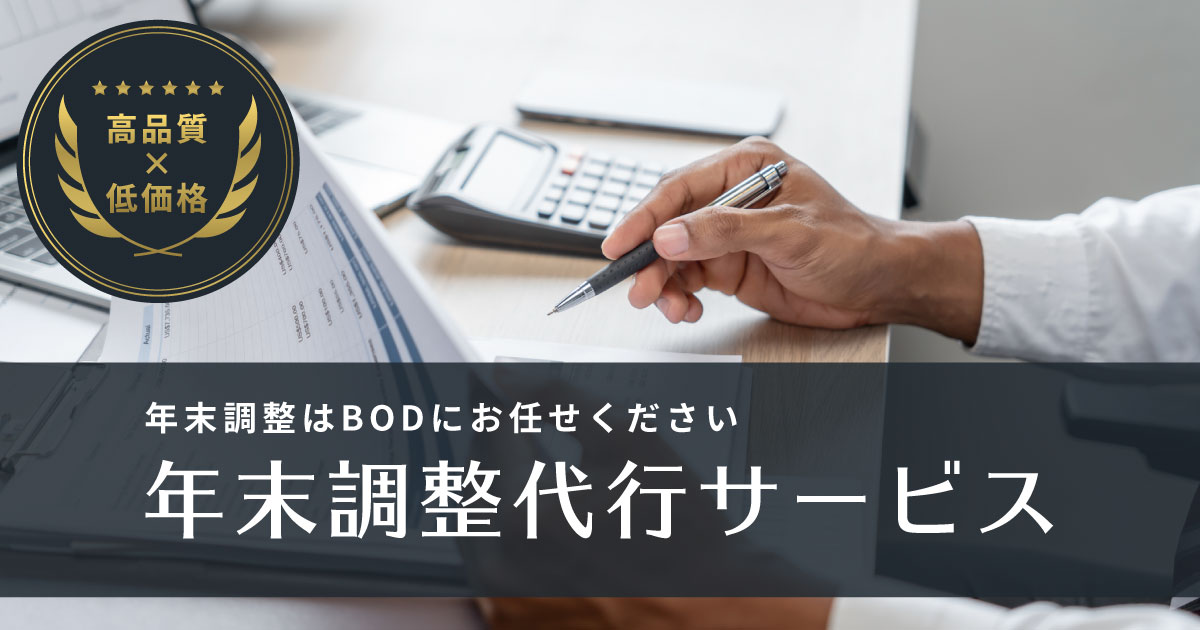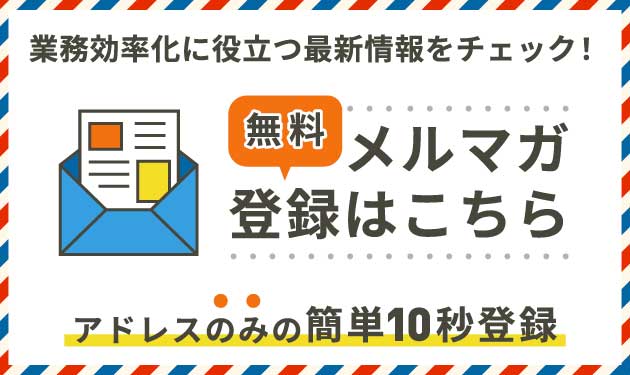年末調整の還付金とは、1年間に給与から天引きされた所得税が、本来納めるべき所得税額より多かった場合に戻ってくる差額のことです。還付金の額は、給与収入や各種控除の状況によって人それぞれ異なります。
この記事では、年末調整の還付金を受け取る仕組みやもらえない人のケースに加え、還付金の計算方法についてもわかりやすく解説します。
▼BODの「年末調整代行サービス」は貴社の運用に合わせて柔軟対応!詳しくはこちら▼
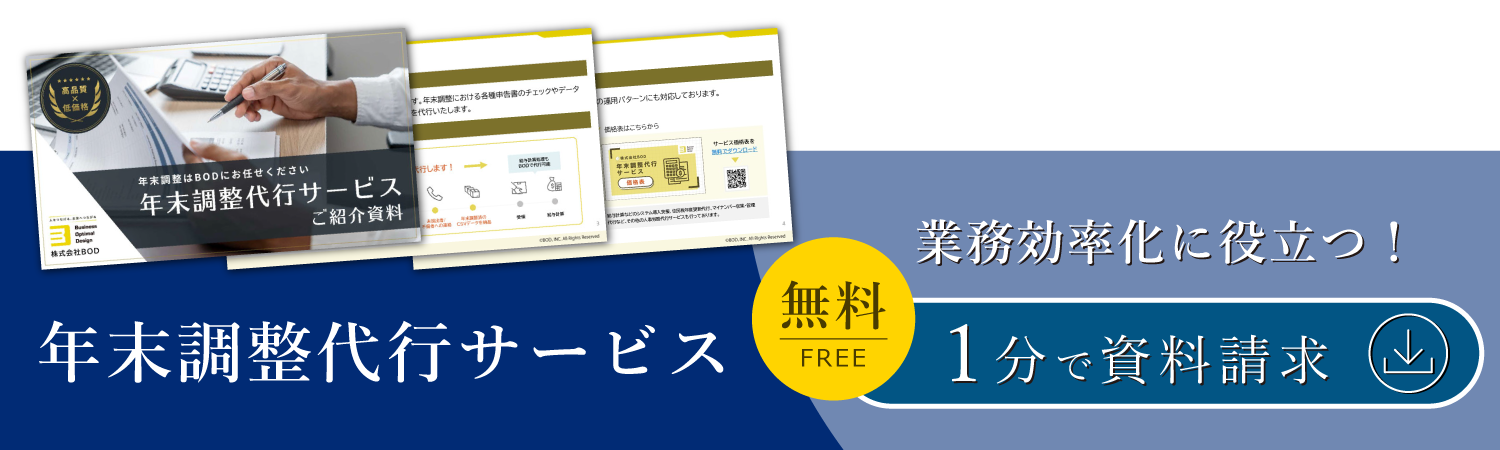
年末調整の還付金とは?
| 年末調整の還付金 | その年の源泉徴収税額が本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に戻ってくる差額 |
給与所得者の場合、毎月の給与や賞与が支払われる際に、所得税が源泉徴収(天引き)されています。
このときの源泉徴収額は、給与から社会保険料(年金・健康保険など)を差し引き、前年の「扶養控除等申告書」で申告された扶養人数などをもとに、国税庁が定める「月額表」に当てはめて一律に算出されます。
ただし、実際に適用される控除額(生命保険料控除・住宅ローン控除など)は、年の途中では確定していません。そこで、年末に改めてその年の収入と各種控除を申告し、正確な課税所得額と所得税額を確定させる手続きが「年末調整」です。
その結果、すでに納めていた源泉徴収税額が多かった場合は、差額が還付金として戻ってきます。逆に、納めた税額が不足していた場合には、追加徴収されます。
※国税庁:給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
還付金はいつ受け取れる?
多くの企業では、12月の給与支給時に年末調整の還付金が振り込まれます。年末調整の書類提出が11月ごろに行われ、その結果が12月の給与計算に反映される、という流れが一般的です。
ただし、給与締め日や支給日が異なる企業では、還付金の反映が翌年1月になる場合もあります。
年末調整の時期になると人事労務担当者は残業続きというケースは多くみられます。こういったケースには、代行サービスの活用をおすすめします。
BODなら、煩雑な年末調整業務を、貴社の運用に合わせて柔軟にサポート!
年末調整で還付金税額が発生する項目
前述のように、年末調整の還付金は「年末調整で算出された所得税額が、源泉徴収された所得税額より少なかった場合」に発生し、本人に還付されます。
年末調整で各種控除の申告を行うことで、最終的に確定した所得税額が、暫定的な源泉徴収額(月額表により画一的に算出し給与から差し引かれていた額)よりも少なくなるケースが多いため、ほとんどの方が還付金をもらえることになります。控除項目について、みていきましょう。
扶養控除
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、控除の対象となる配偶者や扶養親族の有無やその人の所得などの情報を記入するものです。この申告書の内容をもとに毎月の給与から控除する所得税額が決定されるため、一般的に入社時に提出します。
この申告書を提出した後に、出産や親との同居などの理由で扶養人数が増えた場合に控除の対象となります。入社時の情報から変更がないか確認するため年末調整の時期にも会社に提出することが一般的です。扶養家族に変化があった場合には「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の修正を忘れないようにしましょう。

配偶者特別控除
「配偶者特別控除」を受けることができるのは、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者が下記すべてに該当する場合です。
- 婚姻届を提出している配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 控除を受ける納税者本人と同一の生計を営んでいること
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(2020年分以降は、配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合)
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと

保険料等控除
生命保険、地震保険、社会保険などの年間の保険料の支払額に応じて控除の対象となります。生命保険は、一般生命保険料(終身/定期/学資など)、介護医療保険料(医療/がん)、個人年金保険料が対象です。社会保険料は、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料など公的な社会保険料が対象となります。
子や親など自分以外の社会保険料を支払っている場合はその金額も対象となります。

小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の規定に基づく掛金などを支払った場合に受けられる控除です。社会保険料と同様に全額が控除の対象となります。これに該当するものは、以下の通りです。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
- 企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 心身障害者扶養共済制度の掛金(地方公共団体が実施するもの)

住宅借入金等特別控除
いわゆる「住宅ローン控除」のこと。自身や家族が住むための家を取得したり、増改築(リフォーム)工事をしたりしたときに住宅ローンを利用した場合に受けられる控除。
ただし初年度は自分で確定申告をする必要があり、2年目から年末調整の対象となります。所得税額から直接控除を受けられる「税額控除」のため、該当する人は高額な還付金を受け取れる可能性があります。

ひとり親控除
令和2年に新設された、ひとり親を対象とした控除。未婚、あるいは配偶者の生死が不明の状態で、所得48万円以下の子供のいる場合に対象となります。

寡婦控除 ※
夫との死別や離婚後に婚姻していない、扶養親族のいる人が受けられる控除。離婚後で扶養親族のいる場合、死別や夫の生死が不明の場合に対象となります。
障害者控除 ※
自分自身や扶養している家族、配偶者などが障がいを持っている場合の控除。
※寡婦控除・障害者控除はすでに会社に対象であることを届け出ている場合、月々の所得税計算の時点で考慮された金額が算出されています。
還付金を受け取るために必要な書類
年末調整や確定申告で控除の申告をする際、添付が必要となる書類は下記の通りです。発行された書類は紛失しないようきちんと保管しておきましょう。税務署へ出向いて確定申告をする場合は、提出を求められることもあるので、通帳、印鑑、マイナンバー、身分証明書も持参することをおすすめします。
- 保険会社から発行される生命保険料等の控除証明書
- 扶養家族の国民年金、健康保険料などを支払っている場合の控除証明書
- 住宅ローン借入金の年末残高証明書
- 源泉徴収票 など
▼BODの「年末調整代行サービス」価格表をチェック!▼

還付金の計算方法
年末調整で還付金が発生するかどうかは、1年間の給与収入と、控除・税率などを正しく計算することで判断できます。ここでは、還付金の金額を算出する基本的な流れを解説します。
準備しておく書類
年末調整の還付金額を計算する際は、以下の3つの書類を手元に用意するとスムーズです。
・その年の1月〜12月までの給与明細
・所得控除の対象となる生命保険料・地震保険料・iDeCoなどの支払額がわかる書類
・住宅ローンの年末残高証明書
保険料や住宅ローンの書類が手元になくても、概算で計算することは可能です。たとえば、保険料は「毎月の支払額×12」、住宅ローン残高は「前年末残高−(毎月の元本支払額×12)」でおおよその数値を求められます。
計算手順
還付金の計算手順の基本的な流れは下記の通りです。
(1)1年間の給与収入額と源泉徴収税額を集計
(2)給与所得控除を差し引く
(3)所得控除を差し引く
(4)所得税額を算出する
(5)源泉徴収税額との差を計算
それでは、順を追って具体的に見ていきましょう。
(1)1年間の給与収入額と源泉徴収税額を集計
まず、所得税の対象となる課税所得金額を算出するために、その年に支払われた給与・賞与の総額を集計します。通勤手当や立替精算など非課税の支給は除外します。
また、年間で源泉徴収されていた税額も集計しておきます。
※転職している場合は、前職・現職すべての源泉徴収票を合算して計算します。
※12月の給与が1月支払いの場合は、総額に含みません。
(2)給与所得控除を差し引く
給与収入額から「給与所得控除」を差し引きます。控除額は年収に応じて自動的に決まり、令和7年度以降は最低保障額が65万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
出典:国税庁「No.1140 給与所得控除」
(3)所得控除を差し引く
給与所得控除後の金額から、各種所得控除(扶養控除・配偶者控除・ひとり親控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)を差し引きます。
控除額は、勤務先に提出した以下の申告書類に基づいて計算されます。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
その結果、課税所得額が算出されます。
●基礎控除の引き上げ、19歳以上23歳未満の特定扶養親族について、詳しくは「【2025年度 税制改正】103万の壁引き上げ、特定親族特別控除の創設とは」の記事をご覧ください。
(4)所得税額を算出する
(3)で算出された課税所得額に以下の税率を当てはめて所得税額を求めます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
計算式:
課税所得額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
具体例:(課税される所得金額が700万円の場合)
700万円 × 23% -63万6,000円 = 97万4,000円
さらに、住宅ローン控除などの税額控除がある場合は、ここで直接差し引きます。
平成25年(2013年)から令和19年(2037年)までの期間は、ここで算出した所得税額に「復興特別所得税(2.1%)」を加えて、最終的な年調年税額を求めます。
計算式:
所得税額 × 102.1% = 年調年税額(100円未満切り捨て)
(5)源泉徴収税額との差を計算
1年間で天引きされていた源泉徴収税額(1で集計した額)と、④で求めた年調年税額を比較します。
源泉徴収税額 > 年調年税額 … 差額分が還付される
源泉徴収税額 < 年調年税額 … 不足分を追加徴収される
計算式:
年調年税額 − 源泉徴収税額 = 差額(マイナスの場合は還付、プラスの場合は追加徴収)
追加徴収が発生する主なケース
年末調整で「還付」ではなく「追加徴収」になるのは、次のようなケースです。
・その年の途中で昇給や賞与(ボーナス)の増加があり、源泉徴収が不足していた
・途中入社・転職などで、前職分の所得が合算されていなかった
・年の途中で配偶者の所得が増え、配偶者控除が適用外になった
・その年の途中で扶養控除対象者が減った(例:子が就職した)
・扶養控除や保険料控除の申告内容に誤りがあった
このように、年末調整の還付金は「1年間に納めすぎた所得税の精算結果」として戻ってくるものです。
給与明細や源泉徴収票を確認しながら、計算の流れを理解しておくと安心です。
●追加徴収について、詳しくは「年末調整の結果、追加徴収となってしまう原因とは?対応策も解説」の記事をご覧ください。
年末調整で還付金をもらえない人とは
12月31日までに退職をした人
年末調整は、1月1日から12月31日までの間に在籍している従業員を対象に行われます。そのため、年の途中で退職してしまった場合は、年末調整の対象外となり還付金も計算できません。ただし、その年の間に転職した場合、転職先の会社で年末調整を受けることができます(転職した時期によっては時間的な都合でできないこともあります)。転職先の会社で年末調整を行う場合には、前職での源泉徴収票の提出が求められますので用意しておきましょう。
退職した場合や転職先の会社で年末調整を受けられない場合は、確定申告をすることで還付金が戻ってくるケースがあります。年末調整が受けられないのであれば、確定申告を行いましょう。
確定申告をする必要がある人
確定申告をする必要がある人は、年末調整で還付金を受けとることはできません。確定申告をしなければいけない人は、以下の通りです。
- 1年間の給与の合計が2,000万円を超える場合
- 災害減免法によって源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予・還付を受けている場合
- 副業などで2か所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合(源泉徴収票 乙欄の場合)
- 年の中途で退職し、再就職していない場合
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出の人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、前述した通り年末調整で各控除を利用するために必要な書類です。この書類を提出しなければ控除が受けられないため、還付金は発生しません。
申告書自体を会社へ提出していても、控除証明書(原本)等を添付し忘れた場合は、年末調整を受けることができません。この場合、翌年3月15日までに確定申告で控除の申告をすれば還付金がもらえることがあります。
▼電子化で年末調整をスムーズに!「導入前のセルフ診断シート付き」資料はこちら▼

▼年末調整代行について必要な情報が完全網羅されています。こちらの記事をご覧ください。▼
人事・労務担当者向け|還付金対応チェックポイント
年末調整で従業員が正確に還付金を受け取るためには、人事・労務担当者が事前に必要な情報を整理し、適切に管理することが不可欠です。
●控除申告書類の確認・整理
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」など、従業員から提出される書類をもれなくチェックし、申告内容に不備がないか確認します。
●従業員への案内・フォロー
結婚・出産・住宅ローン契約など、ライフステージの変化に応じて控除が変わることを周知し、必要な書類提出を促すことで、申告漏れや計算ミスを防げます。
●業務の効率化
事前に従業員から情報を収集しておくことで、年末調整時期の業務集中による負担を軽減できます。特に、給与システムやExcel、スプレッドシートで情報を整理しておくと、還付金の計算や差額精算もスムーズに行えます。
こうした作業を効率化し、正確な年末調整を実現するには、外部の年末調整代行サービスの活用も有効です。BODの年末調整代行サービスでは、従業員からの控除申告の確認や整理を含め、業務を一括で対応可能。担当者の負担を大幅に軽減しつつ、従業員がスムーズに還付金を受け取れるようサポートします。
よくある質問(FAQ)
- Q年末調整の還付金はいつもらえますか?
- A
年末調整の還付金は、通常12月の給与支給時に支払われます。ただし、企業によっては1月の給与と一緒に支給される場合もあります。還付金の支給時期は勤務先の給与支給スケジュールによるため、詳細は会社の人事・経理担当に確認することをおすすめします。
- Q年末調整で還付金がもらえない場合もありますか?
- A
年末調整で還付金が発生しない主なケースは、1年間の源泉徴収税額が適正で、追加の控除がない場合です。また、年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合や、扶養控除や保険料控除などの申告漏れがある場合も、還付金が発生しないことがあります。
- Q年末調整で還付金を多くもらうにはどうすればいいですか?
- A
還付金を正しく受け取るには、生命保険料控除や扶養控除、医療費控除など、適用可能な控除を漏れなく申告することが重要です。控除証明書の提出や、正確な扶養家族の申告を行うことで、源泉徴収された税額との差額が大きくなり、還付金が増える可能性があります。
【毎年大変な年末調整はBODにお任せください!】
年末調整における各種申告書のチェックやデータ作成、不備・督促対応やファイリングなど、毎年スポットで発生する年末調整業務を代行します。WEB運用、書面での運用、WEB・書面の併用運用にも対応しています!
▼お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ▼