給与計算は、企業にとって毎月欠かせない重要な業務です。従業員の信頼やモチベーションに直結するだけでなく、法令遵守や税務対応など高い正確性も求められます。しかし、制度改正や人手不足、業務の煩雑化により、自社での対応に限界を感じる企業も増えています。
そこで注目されているのが、給与計算業務を専門事業者に委託する「給与計算代行サービス(アウトソーシング)」です。本記事では、給与計算代行サービスの仕組み・業務範囲・料金相場・選び方をわかりやすく解説します。
▼給与計算業務の運用やルールを整理し直したい方に、資料3点セットがおすすめです! ▼

給与計算代行とは
給与計算代行サービスとは、企業が自社の給与計算業務を外部の専門業者にアウトソースする仕組みです。人事労務やバックオフィス業務の効率化を目的に導入されています。
委託先は、社会保険労務士事務所、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業、クラウド型のSaaSベンダーなど多岐にわたります。主に、以下のような業務を代行してもらうことが可能です。
【給与計算代行サービスで対応できる業務】
月次給与計算(基本給、残業代、各種手当の計算)/ 賞与計算 / 勤怠情報の集計・管理 / 銀行振込データの作成 / 給与明細の発行(紙・電子)/ 社会保険・労働保険の手続き / 住民税の特別徴収・更新 / 年末調整
※オプションサービスとなる業務もあります。 詳しくはサービス詳細をチェック!
給与計算代行が必要とされる背景
給与計算業務は、単なる計算作業にとどまらず、法改正への対応、従業員ごとの雇用形態・就業規則の違いを反映、勤怠情報や勤怠管理システムとの連携など、専門性と正確性が求められます。
また、人事労務やバックオフィス業務の一環としても負担が大きく、業務効率の向上やコスト削減を目的に給与計算の業務代行を検討する企業が増えています。
具体的には、以下のような背景からアウトソーシングへのニーズが高まっています。

法改正や制度変更への迅速な対応が困難
毎年のように行われる税制改正や社会保険制度の変更に対し、社内で常に最新情報をキャッチアップし、給与計算に正確に反映させることは容易ではありません。特に中小企業では、法務や労務の専門人材が不足しているケースも多く、対応が後手に回ることで法令違反や従業員とのトラブルにつながるリスクもはらんでいます。そのため、専門知識を持つ代行会社や社労士事務所にアウトソースする動きが進んでいます。
担当者の退職や異動による業務継続リスク
給与計算は属人化しやすい業務の一つであり、担当者が退職・異動した際に、引き継ぎが不十分だと業務が滞る恐れがあります。特に給与計算は毎月決まったスケジュールで行う必要があるため、担当者不在による遅延やミスは企業にとって大きなリスクです。こうしたリスクを回避するために、給与計算代行業者への委託や業務フローの見直しを進める企業も増えています。
ミスによる従業員の不信感やトラブルの回避
給与計算のミスは、従業員の信頼を損なうだけでなく、労使トラブルや法的リスクにも発展しかねません。たとえば、残業代の未払い、控除額の誤り、支給日の遅延などは、従業員の不満を引き起こす要因となります。
信頼できるアウトソーシング先を選ぶことで、スムーズな業務遂行と安心の品質管理を実現できます。
人事・労務部門のリソースをコア業務へ集中
人事・労務部門は、採用、育成、組織開発など、企業の成長に直結する戦略的な業務を担っています。しかし、給与計算のような定型業務に多くの時間を割かれてしまうと、本来注力すべき業務に手が回らなくなります。そのため、人事業務や労務管理の効率化を図るためにアウトソーシングを導入する企業規模は年々拡大し、特に大企業向けのBPOサービスやクラウド連携型の給与計算システムも普及しています。
給与計算代行のメリットとデメリット
給与計算をアウトソーシングすることによるメリットとデメリットについて具体的に解説します。
給与計算代行を利用するメリット
専門家による正確な処理でミスを防止
給与計算に精通した専門スタッフが対応するため、計算ミスや法令違反のリスクを大幅に軽減できます。特に複雑な残業計算や控除処理も正確に行われ、従業員とのトラブル防止にもつながります。
法改正や制度変更にも自動的に対応
税制や社会保険制度の改正があっても、アウトソーシング事業者が常に最新の法令に基づいて対応してくれるため、企業側で情報収集や対応作業をする必要がなくなります。
担当者の業務負担軽減、コア業務へ集中可能
給与計算にかかる時間や手間を削減できるため、人事・労務部門は採用、人材育成、組織開発などの戦略的業務に集中することができます。限られた人材リソースを有効活用することが可能です。
セキュリティ体制が整っている事業者が多い
代行サービス事業者の多くは、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの認証を取得しており、個人情報の取り扱いに関する厳格な管理体制を整えています。自社で運用する際の情報漏えいリスクを軽減できます。
システム導入や運用コストの削減
クラウド型のアウトソーシングサービスを利用すれば、自社で給与計算ソフトを導入・保守をする必要がなくなり、ITコストの削減にもつながります。初期投資を抑えたい企業にも適しています。
▼システム選びで給与計算の未来が変わります!詳しい資料はこちら▼

給与計算代行を利用するデメリット
自社内にノウハウが蓄積されにくい
業務を外部に委託することで、給与計算に関する知識や実務経験が社内に残りにくくなります。将来的に内製化を検討する場合や、緊急時の対応力に課題が残る可能性があります。
代行事業者との連携・調整が必要
勤怠データの提出や従業員情報の更新など、代行サービス事業者との定期的なやり取りが発生します。情報共有が不十分だと、処理ミスや納期遅延の原因になるため、社内の連携体制も重要です。
カスタマイズ性に限界がある場合も
代行サービス事業者によっては、独自の給与体系や就業規則への対応に制限があることがあります。特に複雑な手当制度や、変形労働時間制、シフト制といった勤務形態を採用している企業は、事前に対応可否を確認する必要があります。
情報漏えいのリスク
外部の委託事業者に個人情報を預ける以上、情報漏えいのリスクはゼロではありません。信頼性の高い事業者を選定し、契約時に秘密保持契約(NDA)やセキュリティ対策の確認を徹底することが求められます。
BODの「オンサイト業務委託サービス」なら、スタッフが貴社に常駐して給与計算業務を代行します。既存のセキュリティシステム、運用体制に合わせて作業をするため、情報漏えいリスクを軽減できます。
給与計算代行サービスの料金相場
給与計算代行サービスの利用料金は、従業員数や委託範囲、業者の種類によって異なります。以下は一般的な相場感です。
月次給与計算:1人あたり 500円〜1,500円程度
年末調整:1人あたり 1,000円〜2,000円程度
住民税更新:1人あたり 500円〜1,000円程度
初期費用:従業員数と委託範囲により変動
※システムを新たに導入する場合は、別途費用が発生します。

【例】従業員100名の企業の場合
月次給与計算:100名 × 1,000円 = 10万円/月
年末調整:100名 × 1,500円 = 15万円
住民税更新:100名 × 800円 = 8万円
初期費用:委託範囲により変動
▼BODなら、専門知識と豊富なノウハウで正確・効率的に給与計算を代行します!詳しくはこちら▼
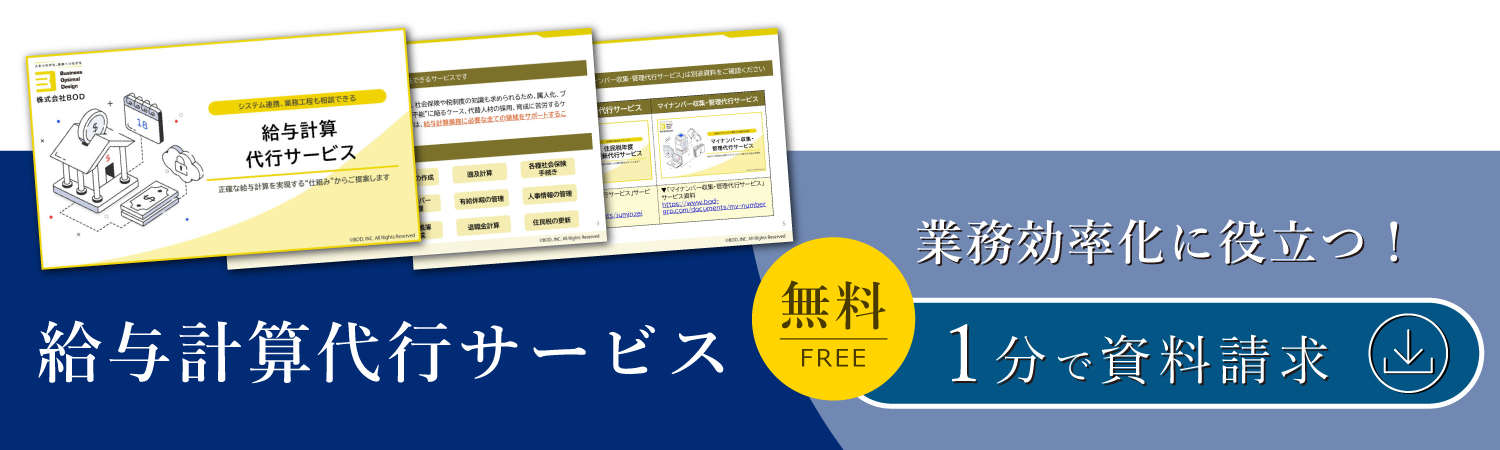
給与計算代行サービスの種類と特徴
1.フルアウトソーシング型
給与計算から年末調整、住民税、社会保険手続きまで一括で委託可能。大企業や人事部門のリソースが限られる企業に適しています。
2.スポット対応型
年末調整や住民税更新など、特定の時期・業務のみを委託。自社で基本業務を行っている企業に向いています。
3.クラウド連携型(システム一体型)
勤怠管理や人事情報と連携したクラウド型のサービス。中小企業やスタートアップに人気で、コストパフォーマンスに優れています。
4.社労士・税理士など専門士業の事務所型
社会保険労務士や税理士、公認会計士など、士業が提供する給与計算代行サービス。専門分野に応じて、法令対応や就業規則の相談も可能です。中小企業や法改正対応に不安を感じる企業におすすめです。
給与計算代行サービスの選び方
自社に合ったサービスを選ぶには、以下のポイントを比較検討することが重要です。
■対応範囲:給与計算だけでなく、年末調整や社会保険手続きも含まれるか
■柔軟性・カスタマイズ性:自社の就業規則や給与体系に対応できるか
■サポート体制:担当者の対応スピードや相談のしやすさ
■セキュリティ体制:個人情報の管理体制やISMS認証の有無
■料金:初期費用・月額費用・オプション費用の明確さ
■実績:同業種・同規模の導入事例があるか

▼度重なる法改正で変更の処理が大変…。BODがそんな悩みを解消します!▼
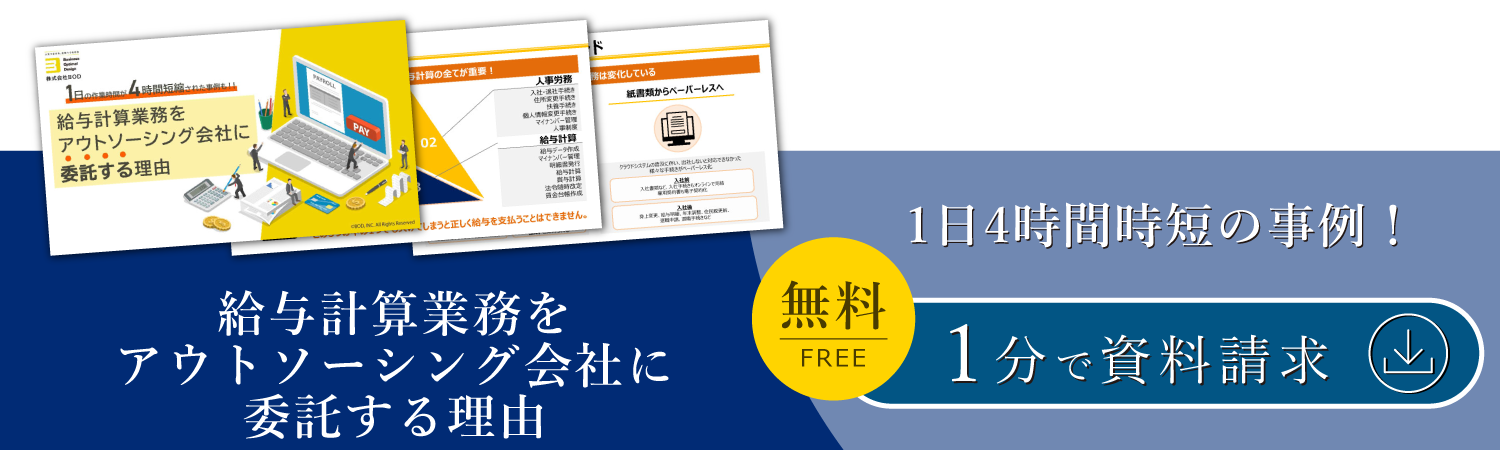
導入の流れと注意点
一般的な導入ステップは以下の通りです。
1)ヒアリング(業務範囲・就業規則の確認)
2)初期設定(従業員情報・給与体系の登録)
3)テスト運用
4)本番運用の開始
5)月次報告・年次業務の実施
【注意点】
契約前に「納品物の形式」「責任分界点」「対応可能な業務範囲」などを明確にしておくことが重要です。

▼BODの「給与計算代行サービス」導入の流れ、詳しくはこちら▼
導入事例・よくある質問
BODの給与計算代行サービス|お客様の声
よくある質問
- Qペイロールとは何ですか?
- A
給与計算業務全般を指す言葉で、給与明細の作成や振込データの作成なども含まれます。
- Q新しいシステムの導入は必要ですか?
- A
クラウド型サービスでは専用システムを使用する場合がありますが、既存のExcelやすでに導入している勤怠システムと連携できる事業者もあります。
- Q従業員によって給与体系が異なりますが対応できますか?
- A
代行サービス事業者の多くは、カスタマイズ対応が可能です。ただし、事前に要件を共有することが大切です。
給与計算代行サービスは、業務効率化と正確性の向上を同時に実現できる有効な手段です。自社の従業員規模や業務内容に合ったサービスを選定することで、人的リソースの最適化や法令対応の強化にもつながります。検討してみてはいかがでしょうか。
BODの「給与計算代行サービス」
お客様からの声:
「1日の作業時間が4時間も短縮されました!」
「法改正による変更にも即時対応で助かりました!」
「給与計算業務のデータフローが整い効率化できました!」
BODでは、給与計算の専門知識とノウハウを持つ専属チームが、万全のチェック体制でお客様の給与を正確に計算します。企業独自の給与計算方法にマッチする人事労務システムを利活用し、業務工程の再構築からご提案、コスト削減へと導きます。
また、勤怠管理との連携、クラウドシステム導入支援も可能です!
\ 給与計算業務をブラックボックス化させません! ぜひご相談ください! /
↓↓↓




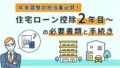

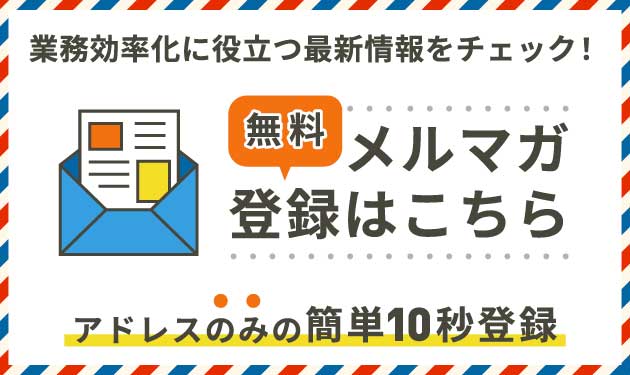
「チェック作業に毎回時間がかかり、19時まで残って作業していましたが、業務工程を入れ替えていただき、15時には作業が終われるようになりました。4時間も短縮されて残業が減り定時で帰れるようになりました」